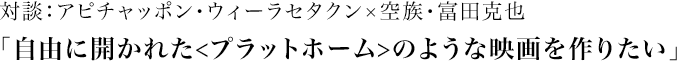『トロピカル・マラディ』(04)、『世紀の光』(06)と、タイから世界へ向けて作品を送り出すごとに見る者たちを驚嘆させてきた映画監督アピチャッポン・ウィーラセタクン。2010年のカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを見事に受賞した彼の監督最新作『ブンミおじさんの森』が渋谷シネマライズで公開されている。
今作を見て私たちが何よりも魅せられたのは、アピチャッポン・ウィーラセタクンがタイの農園地帯で暮らすブンミおじさんたちの姿を通しながら見つめていく、そこに生きる人々の<生>の輝きそのものだ。ときにどこまでも透明であり、ときにどこまでも艶めかしくもある夢幻的な<生>のたしかな存在感が、この映画には確実に根付いている。常連の俳優や撮影クルーたちと共に、アピチャッポン監督は、そんな自身の映画をどのようにして生み出しているのだろうか?あるいは、アピチャッポン監督にとっての「映画」とは?
――こうした私たちの問いの足がかりとなるかのように、今回、アピチャッポン・ウィーラセタクンと、映像制作集団<空族>の富田克也さんによる対談の場を設けることができた。富田克也さん(『国道20号線』)は、個人的にもタイという国に造詣が深く、<空族>としてタイで映画も撮っている新進気鋭のインディペンデント映画監督。『ブンミおじさんの森』をめぐって、このふたりの映画監督たちから、いったいどんな会話が生まれるのか。
アピチャッポン・ウィーラセタクン監督と、新作『サウダーヂ』の公開も待望される富田克也監督が、ここ日本で出会った。
<人生に深く関わっていく映画>
富田克也(以下、富田) とても残念なことに、日本はアピチャッポン監督の作品を見る機会に恵まれているとは言えません。ですが、見ることのできる数少ない作品を目にして、僕が何よりもアピチャッポン監督の映画に親近感を覚えるのは、映画を撮っているあなた自身が周りにいる人々と深い付き合いをしていくことで、作品が作られているということです。僕も、自分の周りにいる人々とのつながりを通じて映画を作ることをこれまで考えてきました。小学校時代からの友人や、作品の制作を通じて偶然出会った人たちと一緒に映画を作ってきたんです。第11回東京フィルメックスで『ブンミおじさんの森』が上映された際に行われたQ&Aを聞いて、アピチャッポン監督もそういった人々とのつながりを大事にされている監督だと思いました。実際に、人々とのつながりによって生まれるそのような魅力が、あなたの映画の画面すべてに現れているんです。どうして監督の個人的な部分に深く関わった映画の作り方を選択されたのでしょうか?
アピチャッポン・ウィーラセタクン(以下、AW) というのも、私にはそれ以外の方法が考えられないからですね。1997年に大学から卒業したとき、私は自分ひとりだけで映画を作りたいと思っていました。ジョナス・メカス作品のような、小規模な映画や、スクラッチ・フィルムのような実験映画を作りたいと思っていたのです。実を言うと、私はとても内向的な人間なんですよ。でも、アメリカからタイに戻ってきたとき、そういった実験映画をタイで作ることは不可能だと気付きました。フィルムを現像するためのラボなどの設備の問題があって、撮影が現実的に難しかったのです。それに、タイの文化事情を考えると、スクラッチ・フィルムのような実験映画はそぐわないように思えました。タイという国は、実験性というよりも、むしろ物語が豊かにある国なのです。そうした背景から、少しずつ自分の創作の領域を広げていきました。
個人的な手法で映画を作っていくためには、やはり個人的な人間関係――撮影クルーや俳優たちとの人間関係です――がとても大事になってきます。たとえばジョナス・メカスは、まるで家族たちと映画を作っているかのように、自分の家や娘を撮っていました。なので、私も自分の家族を作り上げながら映画を撮っていかなければいけないと思ったのです。
私にとって映画作りとは、とても有機的なプロセスだと思っています。それと同時に感じるのは、そのプロセスのなかで年老いていく自分、つまり、過ぎゆく歳月の重みという感覚です。私と一緒に映画を撮っている人たちは、最近、結婚して家庭を持つようになってきました。彼らは私の映画以外の撮影の仕事をして、家庭の生計を立てなければならない状況になっています。ですので、この『ブンミおじさんの森』のような、1年がかりで撮影する映画作りを私はこれからも続けられるかどうか疑問に思っています。フィルムで撮影することは、それだけお金もかかりますから、資金繰りという問題はつねに大きな壁としてありますね。仲間のなかには、「パルム・ドールを獲ったのだから、給料をしっかり払ってほしい」と言う人もいます。昔と比べて、少しばかり複雑な状況になってきてしまいました。
富田何人くらいのクルーたちと撮影をしているのですか?
AW中心的なメンバーはおよそ15人くらいですね。しかし、家族同然のように撮影を共にしているのは、私の映画に出演する常連の俳優も含めて、6~7人ほどでしょうか。私のアシスタントとはとても近しい関係を築きながら撮影をしていますし、美術部の人たちとも、とても仲良くやってきています。ときどき、美術部の人たちの父親になったような気持ちになることがあるんですよ(笑)。もちろん、音響設計者や編集者たちも重要な人物となっています。ちょうどいま、私の映画の編集者をしていた人の監督作品を私がプロデュースしているんですよ。自分の作品で働いてくれたお礼をしているような気分です。
富田僕たちもまったく同じようなやり方で映画を撮ってきました。初歩的な質問になってしまうのですが、アピチャッポン監督は『ブンミおじさんの森』までの映画作品を、35ミリ・フィルムで撮影をされていますよね。当然、資金繰りであるとか、撮影クルーの技術といった問題が、これまで常にあったんだと思います。今回、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞されたことも、実はそういった地に足のついた撮影の積み重ねの結果であると、今作を見てたしかに感じることができました。
以前、僕がペドロ・コスタ監督と対談させてもらったとき(「映画芸術」誌 No.432に掲載)、アピチャッポン監督は彼の友人だとお聞きしました。実はそのときから、アピチャッポン監督とペドロ・コスタ監督の映画作りの方法は、もちろん作品の質は異なるとは思いますけれども、とても似ていると感じていたんです。僕自身も、そういった映画の作り方をしていると思っています。なので、おふたりには非常に親近感を感じてしまうんです。
AWあなたもご自分の映画の家族を持っているということですね。
富田僕たちが撮った『サウダーヂ』(2011年公開予定)という映画には、日本で働いているブラジル人やタイ人の方たちに、やはりノーギャラで出演していただきました。ちょうど1年間ほど撮影をしたんですが、一緒に長い時間を過ごしていると、やはり彼らの人生に深く関わっていくことになります。でも、アピチャッポン監督と同じように、それが今の僕たちの映画の作り方なんです。
<シネマテークの設立と映画のデジタル化>

©A Kick the Machine Films
富田実は、次はタイのバンコクを舞台に映画を撮る予定なのですが、アピチャッポン監督にタイの映画状況についてぜひともお伺いしたいと思います。タイ映画といえば、たとえばアクション映画などがとても盛んに作られていると思うんですけれども、アピチャッポン監督のこの『ブンミおじさんの森』は、どのようなかたちで上映されているのでしょうか?
AW2010年はタイのインディペンデント映画にとって、とても良い年でした。最近、タイにもデジタル上映専門の映画館が出来たんです。もちろん、商業目的の映画館ですが、それがタイの若手監督たちのための映画館にもなっているのです。その映画館チェーンのなかで、『ブンミおじさんの森』も公開されました。幸いなことに、作品の評判も観客動員もとても良かったですね。たしかに、コメディやアクションといったジャンルの娯楽映画はたくさんあります。その一方で、若い監督たちがデジタルによって、違ったタイプの映画を作っているんです。タイには短編の映画作品を集めた映画祭があるのですが、年々その映画祭への応募作品が増えているんですよ。タイにとって、それはすごく良い兆しだと思っています。
富田この『ブンミおじさんの森』のパルム・ドール受賞は、そういった動きの追い風になるかもしれないわけですね。
AWそうなることを願います(笑)。もちろん、こういった動きは『ブンミおじさんの森』の受賞以前からありましたが、映画館チェーンがインディペンデント映画に、新しいマーケットとしてもっと目を向けるようになるきっかけになればと思っています。
実を言うと、私の夢はタイの北部にあるチェンマイに、アート系のシネマテークを開設することなのです。日本でも、シアター・イメージフォーラムといった映画館に行くと、ものすごく刺激を受けます。それに、台湾には侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督が経営している映画館がありますよね。実は、チェンマイでのシネマテーク開設のために、土地探しをすでに始めているのです。以前、ソウルの映画祭に招かれたとき、その映画祭のディレクターがアート系の映画館をオープンしたと聞きました。彼は映画監督でもありますが、その映画館を開設したことによって、自分の生活がいかに苦しくなったかを話してくれました。もしかすると、映画作りそのものを犠牲にしないと、そういった映画館の開設はできないのかもしれないのかもしれません。良い映画館を運営していくためには、映画監督のままではいられないのではないかと躊躇してしまうときがあるのです。ですが、侯孝賢のように、映画監督をしながら、自分の映画館を成功させている人がいることはたしかです。彼がその映画館を上手く経営できているのは、同時に広告代理店も経営しているからなのだと思います。彼の広告代理店は、経営がとてもうまくいっているのです。侯孝賢は、芸術的な感性と、そういった商業的な面での才能をバランス良く持っている人なんですよ。私には両方を成り立たせることはできないのではないかと少し不安に思います。
ところで、蔡明亮(ツァイ・ミンリャン)監督は今どうしているんでしょうね?実は、彼は自分の喫茶店を始めたそうなんですよ。私もどちらかと言えば、蔡明亮がやっているような、喫茶店くらいの小さな商売向きなのかもしれない(笑)。ですから、アート系のシネマテークというのは、私にはまだ少し現実性がない話なのかもしれませんね。
富田実を言うと、僕たちも似たようなことを考えていました。やはり、映画を撮っていくことだけで資金繰りや自分たちの生活を成り立たせていくことはとても難しいんです。もちろん、映画監督が自分たちで映画館を持つということは、本当に理想的なことだと思うんですが、東京のような場所でそれを経営していくのはやはりとても難しい。でも実は、これは内緒の話なんですが、最近僕たちは八百屋の経営を始めたんです(笑)。
AWすごい! でもどうして八百屋なのですか?
富田僕たちが映画を撮っている山梨県という場所は、とても田舎なのですが、そこで収穫される新鮮な野菜を東京に持ってきて売るんです。「産地直送」というかたちで。
AWああ、なるほど。東京でプレミアムな野菜を売ることができるというわけですね。そういえば、蔡明亮も海外から輸入したプレミアムなコーヒー豆を売りにしているそうですよ。
富田蔡明亮さんの喫茶店とはかなり異なる商売ですが(笑)。僕たちは今そのようなことを始めているんです。でも、本当にアピチャッポン監督にはぜひチェンマイにシネマテークを作っていただきたいと思います。
AWそうなると本当に素晴らしいと思います。ですが、作るとすればデジタル上映専門の映画館になるでしょう。映画は今、デジタル上映というよりコストのかからない形態が主流になっていっていますよね。なので、デジタル技術によって、映画館の経営ももっとお金のかからないものになるという期待はあるんです。
――たとえば、映画がデジタルになっていくにつれて、これからのアピチャッポン監督の映画の作り方や表現の方向性も変わっていくのでしょうか?
AWそうなると思います。私は映画だけではなく、いわゆるヴィジュアル・アートといった映像の世界にも関わっています。そういった分野では、私はデジタル・ヴィデオによってより抽象度の高い短編の映像作品を作ったりしているのです。でも、映画制作の現場では、私は「この映画はこういったコンセプトと方向性で撮ります」ということは事前に決して言いません。技術の革新がどういった方向に進んでいるかを捉えることは難しいですし、自分自身も、そういった大きな流れのなかで常に変わっていると感じているからです。なので、今ここで自分の映画がどういった方向に向かっているかを明確に述べることはできないんです。
――アピチャッポン監督は素人の俳優をよく起用されていますよね。『ブンミおじさんの森』では、そういった俳優たちの自然な存在感が捉えられていて、本当に素晴らしいと思いました。たとえば、アピチャッポン監督が抽象度の高い実験的な映画を撮ろうとする際に、そういった素人の俳優たちは、とまどいのようなものを感じたりはしないのでしょうか?
AW常連となっている俳優たちとは、一緒に映画を作りながら、私と一緒に歳を重ねているという感覚があります。そうすることで、ある意味、彼らは同じような世界観を共有していくことになるんですね。たとえば私が、どれだけ抽象的なことをイメージしていても、彼らは問い返すことはあまりしません。それは、彼らとのあいだにある種の信頼関係が築かれているからだと私は思っています。一緒に映画を作っていくことで、私の映画の流れに身を任せるように出演してくれているという気がするのです。それに、私が彼らに何か要求する場合でも、とてもカジュアルな友人としての会話になりますね。友人関係の延長として、映画の撮影をすることができるんです。彼らが完成した映画を見てから、「ああ、こういうことだったのか」と私の考えを納得してもらえるときもありますし、逆に、「やっぱり解からないな」と言われるときもあります。どちらにせよ、作品の抽象度というものが、彼らと私の共同作業の大きな壁となっているように感じたことはないのです。俳優たちとの関係だけでなく、撮影クルーとの関係にも同じようなことが言えると思っています。