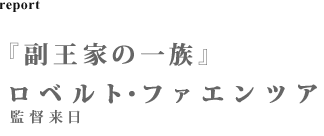19世紀イタリア統一運動のさなか。スペイン・ブルボン家の副王家(国王代理の行政官)の末裔である、シチリアの貴族ウゼダ家。この名門一家の当主である封建的な父と、彼に反発する息子との愛憎を中心に、いま「イタリア」と総称される土地々々が経験した激動の時代を描く『副王家の一族』。原作はフェデリコ・デ・ロベルトの小説『副王たち』。かつてルキノ・ヴィスコティが翻案した小説『山猫』の源流とも言えるこの小説を念願叶ってついに映画化したというヴェテラン監督ロベルト・ファエンツアが、日本公開を記念して来日した。
この作品で何よりまず目を惹くのは、ウゼダ家の豪勢な屋敷であり、また忠実に再現されたその内部だろう。「あの建物は、原作者ロベルトが実際に描いた一家の末裔が実際に所有している屋敷です。いまは博物館になっていて家具類はありません。ですので当時を再現するため衣装やセットには非常に手を尽くしました」。そして、まさにヴィスコンティ映画を思い出させるような衣装を手がけたのは、偉大なるミレーナ・カノネロ。スタンリー・キューブリック作品(『時計じかけのオレンジ』『バリー・リンドン』)で実力を発揮し、『コットンクラブ』や『ゴッドファーザー PARTⅢ』(ともにF・F・コッポラ)、そして近年では『マリー・アントワネット』(ソフィア・コッポラ)など、クラシカルな衣装を手掛けさせたら右に出る者なしのデザイナーだ。とはいえ、もちろん衣装に関しては苦労も多かったという。「19世紀の衣服は、その着方もいまとは違います。コルセットにしても非常に時間が掛かります。俳優たちは朝4時に起きて、数時間掛けてメイクをしたり衣装を着ていくのです。衣装のせいで、なかには失神してしまう女優もいたくらいでした」。
こうした外面的な絢爛さに支えられつつ、『副王家の一族』には「イタリア」という複雑な「国」への、おそらく皮肉さえ込めた監督の真摯な思いが込められている。「イタリアというのは、いまひとつの『国』として捉えられていますが、基本的にはアメリカ合衆国のように複数の州で構成されています。当然昔はもっとその色が濃かったわけです。1860年に一応は統一されましたが、いまでもとくにシチリアでは独立志向が強い。当時多くの『イタリア人』にとって、シチリアが『イタリア』であるとは認識されていませんでした。また20世紀に入り、第二次大戦が終わり、ファシズムが終わった時点では、シチリアにはイタリアから離れようという動きもありました。それほどイタリアへの思い入れが弱い地方なのです。現在まで続くこうした問題が、この作品には強く反映されています」。
イタリアは生まれた。ではイタリア人はいつ生まれるのか……。そんな台詞が主人公の口から聞かれるとき、わたしたちは、これまで幾人もの監督たちが描いてきたイタリアの熾烈な歴史に思いを馳せるだろう。たとえば20世紀初頭のファシズム誕生を描いたベルナルド・ベルトルッチ監督(ファエンツア監督とほぼ同世代だ)の『1900年』。ウゼダ家の君主を演じた俳優ランド・ブッツァンカの顔が少しロバート・デ・ニーロを思わせ、またそのサディストぶりがどこかドナルド・サザーランドの狂気に繋がる気配を持つように、『副王家の一族』を『1900年』の前史として考えるのも、また一興だろう。
11月7日(土)、Bunkamuraル・シネマほか全国順次ロードショー
配給:アルシネテラン
公式HP:http://www.alcine-terran.com/ichizoku/

『副王家の一族』
2007年/122分/シネマスコープ/カラー
監督:ロベルト・ファエンツァ
脚本:フランチェスコ・ブルーニ、アンドレア・ボルボラーティほか
撮影:マウリオ・カルヴェージ
衣装:ミレーナ・カノネロ
出演:アレッサンドロ・プレツィオージ、ランド・ブッツァンカ、クリスティーナ・カポトンディ、グイド・カプリーノほか
©2007: Jean Vigò Italia, RAI CINEMA Spa, RAI FICTION Spa, Isitut del Cinema Català;
取材・構成:松井宏