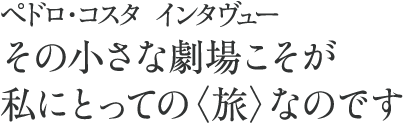すでに日本において確固とした支持を集め、新作を心待ちにするファンの多いペドロ・コスタの新作『何も変えてはならない』が公開される。
本作は女優ジャンヌ・バリバールを迎えて撮影された音楽についてのドキュメンタリーであり、女優についてのポートレートであり、そしてまた緊張の漲る小さな空間に親密な眼差しを投げかけた〈映画〉でもある。
チョンジュ国際映画祭に参加したその足で来日したペドロ・コスタにインタヴューを行った。
――まずはじめにジャンヌ・バリバールとの出会いについて教えていただけますか?
PCジャンヌとは2003年のマルセイユ国際ドキュメンタリー映画祭で審査員として出会いました。コンペティション部門の審査をしたのですがが、ほとんどの作品がひどかったんですね。ジャ・ジャンクーの『In Public』(2001)に唯一賞を与えたのですが、それ以外は本当にひどかったので、私たちはふたりで外のカフェに行って音楽や映画について色々話していました。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの一番最初のディスク、バナナのジャケットのものをジャ・ジャンクーのために二人で買ったりもしました。でもジャ・ジャンクーはヴェルヴェッツについてはまったく知らなくて、曲を聴いたことすらなかったんです。まあとにかくそれがジャンヌとの最初の出会いでした。
――そのような出会いに始まって、友人であるジャンヌ・バリバールのそばに小さなカメラを持ち込んで撮影をしようと思ったのは自然ななりゆきだったのでしょうか?
PC実はこの映画を始めるにあたって、もう一人別の友人のことを話さなければなりません。それがフィリップ・モレルという録音技師です。彼が私たちふたりをこの映画を撮ることに駆り立ててくれた人なんですね。ところが自分自身はこの映画を撮ることについて――特に音楽の映画を作るということについて――ためらいがあり、すぐに始めるということはありませんでした。
フィリップ・モレルが間に入っていたことは、ジャンヌ・バリバールを女優としてではなく、音楽家として見つめることに影響したのでしょうか?
PCたしかにフィリップ・モレルがいてくれたおかげで歌手としてのジャンヌ・バリバールに着目して映画を撮ることを決意したわけですが、ただすべての歌手というのは同時に女優でもある、演じ手でもある、役者でもあります。ジャンヌ・バリバールも実際に歌手であると同時にそこで演じているわけですよね。
――『何も変えてはならない』の撮影期間は2004年頃だと思いますが、これは『コロッサル・ユース』の撮影時期と近いですよね?
PC実際にどの時期に撮影が始まったか、あるいは撮影がどのように前後していたかというのはよく覚えていませんが、2本の短編と『コロッサル・ユース』を撮った時期は重なっていて、その間に時間を見つけては『何も変えてはならない』の撮影をしていました。6月に3週間の時間があればそこで撮影をして、さらにまた9月にも3週間撮る、というふうに、空いた時間を見つけては撮影をしていました。ジャンヌ・バリバールの方から電話が来て「コンサートに来ないか」と呼ばれたこともありました。この映画のなかで中心的に描かれているのは録音のリハーサルのシーンですね。それはロドルフ・ビュルジェの自宅兼スタジオで、2006年に1週間そこで撮影をしました。ですから、この映画はある意味で友だちの間で完成した映画と言うことができると思います。
――スタジオ内に、しかも制作期間中というプライベートな空間にビデオカメラを持ち込むにあたって、撮影に関するルールなどはあったのでしょうか?
PC私の映画は常に予算が限られているので、ひとつのカメラ、ひとつのマイクしか置けないし、照明もなるべく自然光を使わなければいけないわけです。ただ、それ以外の条件や制約はありませんでした。先ほどプライベートと仰りましたが、プライベートというよりはむしろ親密な空間だったと思います。ジャンヌ・バリバールは私を信頼してくれたし、そのことでロドルフや他のミュージシャンたちも私を信頼してくれた。他の撮影のときでも同じですが、そういう信頼関係の上に映画は成立しています。だから自分がそこで撮影することによって混乱が生じるとは考えていません。友人になること、そして相手を知るということ。それによってここに親密な空間ができ、それがこの映画の基盤となっていると思います。
――親密さをそのままカメラひとつで記録するということと同時に、先ほど『コロッサル・ユース』と撮影期間が重なっているというお話もありましたが、その頃にある程度人工的に映画を作り込むことに対して意識の変化があったのではないかと感じます。たとえば『何も変えてはならない』のスタジオ・シーンでの録音は、ライン入力の音源とマイクを使って録った音源をミックスして作り上げているのではないでしょうか?
PC少しテクニカルなことになりますが、たしかに一方でリハーサルやオペラ《ペリコール》を歌っているシーンは私が撮影をして、他に録音技師がいます。最初はフィリップ・モレルでしたが、彼が途中で亡くなったので、それ以後は他の録音技師が録っています。それは言ってみれば映画と同じようなやり方です。つまり、映画で台詞を録るときと同じように彼らの間にマイクを設置して、全体の音を録る。ダイレクトで録ることをモノラル録音と言うわけですが、そういうやり方で録っている。もう一方で、コンサートのシーンでは、ケーブルでつないだコンサート全体の24個ぐらいに分けられている音源――つまりジャンヌにはジャンヌの音源があって、ロドルフにはロドルフの音源がある――それを最後ひとつにまとめなければいけません。映画を作るときになってそれをミックスするという作業があります。
しかし今言ったことは技術的な側面だけのことであって、心情的にはモノラル録音でやりたかったんです。ひとつのマイクで全体を一緒に録るというモノラル録音は、60年代後半にステレオ録音が開始されるまでは主流の方法でした。私がなぜモノラル録音でやりたかったのかと言うと、ラディカルな側面とはまったく関係がなくて、モノラル録音がいいと言ったのはジョン・レノンだったからです。ジョン・レノンは最初のビートルズのディスクを出すときに、プロデューサーのジョージ・マーティンがステレオ録音をすると言ったことに非常に抗いました。なぜかと言うと、それはここに友人たちみんなが一緒に集まって演奏をしているのに、こっちにベースがいて、こっちにボーカルがいて、こっちにギターがいて、ドラムがいて、というふうにバラバラになることに対して反対したかったからです。1年ほど前にビートルズのすべての音楽がリマスターをもとにして世界で同時に発売されましたが、そのときにポール・マッカートニーはもし今ビートルズのCDを買うのなら、モノラルで録られた音源を買ってくださいという声明を出しましたよね。
――その一方で、ジャンヌ・バリバールがヘッドフォンをつけてレコーディングをしているシーンでは、ミックス室、録音室の方では音が鳴っているのに、バリバールが歌っている空間の音声はアカペラで聴こえてきます。それはバリバールの孤独――そばに仲間がいるから孤独ではないんですけれども――を音を作り込むことによって表しているようにも見えます。それぞれの空間がひとつのカメラで捉えられているのに、あたかも出来事は同時に進んでいるように音の面で再構築している。そういったところで同時録音、モノラル録音以外もわりと使われていると思うのですが、その真意、あるいは全体についてはいかがですか?
PCもちろんあのシーンは意識的に準備をして取り組んだところです。あそこは完全なアカペラではないですよね、彼女はヘッドフォンをしているけれども、かすかに漏れてくる音があります。マイクでそのわずかに漏れてくる音も録っているのです。それが少しだけ聴こえてくるので完全なアカペラではありません。ただし、いま言ってくださったように、非常に感動的なのはジャンヌ・バリバール自身の不安や苦しみ、孤独といったものがそのシーンによって浮かび上がってくることです。創造行為というのはある意味で自分の身を危険に晒すことで、それが浮かび上がってきているのだと思います。
――バリバールは見ているこちらも緊張を強いられるほどに周りに仲間がいながらも孤独を抱えているように見えます。その周りの男たち――ギタリストなり録音技師なりピアニスト――には、わりと気ままな、緊張を緩和するような振る舞いがあると思うのですが、バリバールが強いる緊張の持続に差し込まれる男たちというのは、一体どういう存在なのでしょうか?
PCこの映画を撮るときに決意したことなのですが、特にロドルフ・ビュルジェのスタジオでリハーサル風景を撮影するときには、まず音楽の仕事――実際に作曲をしたり、それを修正したりする作業――そのものを撮りたいと思いました。もうひとつは、登場する4人――特にふたり――彼らに眼差しを向けるということをしたかった。そのふたりとはロドルフとジャンヌですが、彼らの――もしこう言ってよければ――「愛の関係」に眼差しを向けたかったのです。そこでロドルフはジャンヌを助ける、ジャンヌはロドルフを賞賛するというような態度をとっていて、それを私はもっと見たかったのです。ですからこれは人間の関係なのです。私は別に音楽の技術的な側面ではなくて、ここに出てくる4人の孤独にもっと眼差しを注ぎたかったのです。そこにはたしかにある運動のようなものがあって、和らいでいくときもあれば、そうでないときもある。その変化が私にとって感動的なのです。みんなでなにかをやっていて、その関係が実際に動いている――その共犯的な部分が見たかったのです。私がいつも残念だと思うのは、映画にはこういうグループの編成が少ないということです。映画ではいつも監督ひとりが孤独で、苦しまなければならない。そういうことが音楽の作業に比べて大きいと思います。
――〈共犯〉という言葉を聞くとジャック・リヴェットの名前が浮かんでしまうのですが、以前『ヴァンダの部屋』公開の際のインタヴューではそのような共犯関係は作りたくないと仰っていたと思います。なにかそれ以後に変化したものはあったのでしょうか?
PCたしかにリヴェットであれば4人の友人であると同時にミュージシャンであるような人と映画を作る思います。ヴァンダの映画を構成している要素というのは3つあって、ひとつはヴァンダであり、もうひとつは自分であり、3つ目にカメラというものがあったのです。カメラがなければヴァンダは自分自身が探しているものがわからない。そしてカメラがなければ私自身もヴァンダという人間を見ることができない。それ以前に私が関わった撮影は、たくさんの人に囲まれていました。なにかを見つめるということに対して非常に多くのフィルターがかかってしまっていた。それが、『ヴァンダの部屋』では、カメラを通してヴァンダを見つめるという行為においてそのようなフィルターがなくなったのではないでしょうか。そういうことからも『ヴァンダの部屋』という作品でもヴァンダとのあいだにある種の共犯関係が――『なにも変えてはならない』と同じように――あったと思います。
――『何も変えてはならない』はモノクロですね。画面を見ると20年代のサイレントホラーのような印象すら受けてしまいます。この映画にはサイレントでミュージカルをやるといういささか矛盾した、同時に野心的な試みが感じられます。
PCご存知だと思いますが私の映画はパナソニックの小さなビデオカメラで撮られています。なので当然カラーで撮っているわけです。『何も変えてはならない』もはじめはカラーで撮られています。ところが編集をしていく段階で――私はいつもパトリシア・サラマンゴという女性と一緒に編集をしているのですが――彼女と実際に撮影された素材を並べて見たときに、コンサートシーンの照明がどうしても気に入らなかったのです。ふたりともそれが嫌でした。ロックのコンサートというものは、武道館でもスターパインズでもニューヨークでもパリでも同じだと思うのですが、照明がまったく良くないのです。例えばストロボをやたらに焚いたり、効果を山のように使ってなにか心理的なことを説明してしまったり、扇情的であったり。たとえば静かに歌ってるときは白っぽい光で、激しく歌うときは赤っぽい光を使うとか、そうしたことが私はとても嫌いです。そんなある日、モニターのスイッチをひねった途端、カラーだった画面が単色化されたのです。それがとても良かったので、じゃあすべて単色化してしまおうということになったのです。もともとモノクロでやろうと考えていたわけではなかったのです。ただし私自身は――結果的ではありますが――モノクロになったことに非常に満足しています。つまり、別の次元が開かれている。具体的に例を挙げると、ジャンヌのクロースアップでは、ジャンヌの歯だったりノドだったり、そういう部分がよく見えています。身体的/肉体的な部分がカラーのときよりも非常によく見えている。これはジャック・タチの言葉だったと思いますが「色は人の気を散らす」、まさにその通りであって、ジャンヌ・バリバールのクロースアップは、モノクロにしたことによって彼女自身が持っているものとは別の要素を出す結果になったと思います。
――変化させることによって別の要素を引き出すということに躊躇はありませんでしたか?
PC色を変えて、単色化するのはもちろん怖いことです。それがいわゆるアーティスティックさだと思われてしまうような危険もあります。この作品はなにかに抗うために作られたものではありませんが――先ほどモノラル録音のお話もしましたが――今日、20年代と同じようにモノクロで映画を作り、かつそれを35mmにブローアップしてネガを作るというのは非常に困難な作業です。そのような現在のシステムに反抗しようと思っていたわけではないのですが、消えていくもの、あるいは死んでいくもの、そういうものを留めておきたいとは思っていました。モノクロで撮るということがこの映画のドキュメンタリー的な要素を薄める、むしろフィクションの方へと向かわせていると思うのです。フィクションが持つ幻想性をより強く出す方向に向かわせたのだと思います。
――この映画では撮影場所として日本も訪れていて、カメラを持って初めての〈旅〉をしたと言うこともできると思います。
PC旅をしなければ映画は作れないわけだし、実際に映画が様々な場所で公開されることで私は一種の旅をするわけですが、ひとつ言っておきたいのは、この作品で描かれているのは〈部屋〉なのです。ロドルフのスタジオだったり、コンサートホールだったり、それらは〈部屋〉という空間です。私はむしろ部屋のなかで旅行をする、部屋にいながら旅行をするということがとても好きです。空間の一部が私の領域で、私はそこで映画を撮る。その中で旅行をする。映画において私が好きなのはこうした小さな空間です。それは廊下だったり、最後のリハーサル室のようなところだったり、――あるいはもっと具体的に言えば――壁だったり、そこに映し出される影だったりするのです。壁と言えばアントニオーニが「壁というものは映画のなかでもっともスペクタクルな効果がある」と言っていたと思いますが、この映画は自分がいままで作ってきた映画の中でも、ひときわ小さな光と影の要素に満ちています。それはそこに小さな劇場があるような感じで、その小さな劇場こそが私にとっての〈旅〉なのです。
取材・構成:山﨑雄太、宮一紀
写真:鈴木淳哉(ポートレート)