アラン・ギロディ インタビュー
秘められたものと明らかなもの
アラン・ギロディの映画にはいつも秘密がある。初長編の『勇者に休息なし』の「最後から2番目の夢」をはじめとする初期作品における謎の固有名詞、『湖の見知らぬ男』の殺人や、『ノーバディーズ・ヒーロー』のホームレスのアラブ人青年ははたしてテロリストの一味なのか否か、など。だがそのうちの一本でも見れば明らかなのだが、謎が解けることがカタルシスをもたらすことなど決してなく、不明な点が払拭されようがされまいが、あっけらかんとそれはそれとして、ある。
最新作『ミゼリコルディア』では、ジェレミー(フェリックス・キシル)は殺人を犯した夜のことを人から尋ねられるたびに嘘を重ねる。二転三転する彼のアリバイに、周りの人物たちは疑いを深めていく。一方で、この映画では、奇妙に思えるほど頻繁に、登場人物たちがジェレミーに「きみは〇〇のことが好きなのか?」と聞く。事件の謎とはさして関係ないところで投げかけられる質問に、駆け引きなどもなくジェレミーは素直に答えているように見える。
アラン・ギロディ(AG) ジェレミーという人物は、ミサの時に神父の手助けをする侍者のようなとても信心深く善良な側面と、シリアルキラーのような道徳を逸脱した側面との、両面を併せ持っていると思います。だから彼が結局そのどちら側にいるのかを私たちは決して知ることができない。
彼はあの夜の出来事については嘘をつき、周りの人々は彼の言葉に惑わされます。ですが、彼は嘘をつく必要がないところでは正直なのだと思う。彼が他の人々に対して持つ欲望は、彼にとっては隠すべきことではない。だから「〇〇のことが好きなの?」という問いにする彼の答えは、嘘のないものだと思います。
登場人物たちにとって謎である、ヴァンサン(ジャン=バティスト・デュラン)が失踪した晩にジェレミーはなにをしていたのか?という問題は、現場を目撃した観客たちにとっては全然謎でもなんでもない。一方で、登場人物たちにとっては自明なことであるかのようにやりとりされる好意や性的な関心は、観客にとっては必ずしもそうとは限らない(え?この人はあの人のことが好きなの?え?あの人も?といった具合に)。隠されたものと、隠しもせずさらけ出されたものとが、モザイクのように組み合わされていく。
そして欲望が包み隠されるべきものではないのは、なにも『ミゼリコルディア』に限った話ではない。『湖の見知らぬ男』の全裸で性器を隠そうともしない湖の周りの男たちや、『ノーバディーズ・ヒーロー』で屋外まで響き渡るイザドラ(ノエミ・ルヴォウスキー)の喘ぎ声のように、性的な欲望は秘められた小さな部屋から広い場所へと飛び出していく。しかし『ミゼリコルディア』にはギロディ作品としては珍しいことに(!)性行為のシーンが存在しない。
AG『ミゼリコルディア』では、セックスの行為そのものは描かないことを試みました。つまり、欲望はいたるところに蔓延しているのに、満たされ充足することはない、そういう作品になっています。
それが神父が重要なキャラクターとして登場する理由でもあると思います。しばしば人は神父を性的なものからかけ離れた存在として思い浮かべがちです。性生活とも恋愛感情とも無縁な生活を送り、すべてを神に捧げ、結婚することもなければ、子供を持つこともない、そんな人物として。
その一方で、真逆の伝統もあります。フランスにはchanson paillardeという伝統的な猥歌があるのですが、そこには必ずと言っていいほど僧侶が出てくる。彼らの性生活を揶揄するような歌が非常にたくさんつくられるほど、聖職者の性欲は昔から非常に関心を持たれていたのだと思います。実際、近年でも聖職者による性加害のスキャンダルは多いですしね。ある意味で聖職者の欲望は否定された欲望と呼べるのかも知れず、僧侶の過ち、彼の性的な欲望についての映画をつくるというのは悪くないアイディアだったと思います。

『ミゼリコルディア』
©2024 CG Cinéma / Scala Films / Arte France Cinéma / Andergraun Films / Rosa Filmes
ないとされるところにある欲望、否定された欲望であるフィリップ神父(ジャック・ドゥヴレ)の欲望は、秘密の告白という手段によって観客の目に明らかにされる。しかも、告解という儀式によって、本来聞くべき立場と秘密を告白する立場とが逆になった転倒した儀式として。
AG ええ、あのシーンは非常に大事なシーンです。あのシーンではおっしゃるように本来告解を聞く側である神父が告解を行うという転倒があります。彼らの立場が逆転しているという点に興味を持ちました。
ですが、仮にもし逆転がなく、神父が信徒の告解を聞くというかたちだったとしても、実際の告解というのは全然あんなものではないのです(笑)。実際には、仕切りの向こうの聖職者はただ黙って信徒の告解を聞きます。それがどんな告解であれ、途中で質問をはさんだりはしません。そしてただ最後にゆるしを与えるのです。だから映画の彼らの会話は、告解室で行われるものというより、テーブルをはさんで行う議論にむしろ似ていますね。
しかしそれでも、告解の儀式であることが映像の上では重要だったのです。つまりふたりの間の仕切りです。お互いをよく見ることができず、影の中にうっすらとだけ見ることができるふたりが話していることが大事だったのです。
告解室の仕切りが、それをはさむふたりの人物の顔を影の中に隠してしまうのだとしたら、それとは真逆に、まるでその存在を誇示するように画面の中に登場するものが『ミゼリコルディア』にはいくつかある。たとえば、死体が埋められているのはここですよ!と主張するかのような、季節外れのモリーユ茸。そして、ジェレミーが眠る寝室の、ベッドサイドにこれ見よがしに置かれたデジタル時計。
AG 今回の物語では時間が何時かを知ることが重要になります。事件の流れを把握することに関係しますから。これもある意味で儀式的なことと言えるのかもしれません。なぜならわれわれは日常生活でいつも時間を確認してばかりいるのですから。そして、時計の時刻はヴァンサンが仕事のためにすごく早起きして出かけることを教えてくれます。朝というよりも真夜中といったほうがいいような時間に、ヴァンサンはジェレミーを起こします。眠りを妨げるという行為は、つねにとても暴力的なものです。

『ミゼリコルディア』
©2024 CG Cinéma / Scala Films / Arte France Cinéma / Andergraun Films / Rosa Filmes
ジェレミーの眠りを妨げるのはヴァンサンだけではない。マルティーヌ(カトリーヌ・フロ)や警察官(セバスチャン・ファグラン)もまた眠る彼から事件に関する寝言を聞きだそうとし、結果的にジェレミーを起こしてしまう。他の誰かが寝ている間に寝室に侵入してくるという、普通に考えれば恐怖を覚えるはずのシチュエーションだが、悪夢のように不条理な状況が繰り返されるほど、なんだか笑えてしまう。
AG おっしゃるようにいろんな人がジェレミーの寝室を訪れては、寝言を聞き出そうとします。繰り返すという行為自体におかしみを覚えるから、というのもひとつの理由ですが、私の作品ではしばしば同じ出来事が繰り返されます。人々が彼ら自身の行為を繰り返すのを見るのが私は好きなのです。そして興味深いのは、ほんとうにまったく同じことが繰り返されるわけではないということです。繰り返しのたびに、なにかがほんの少しずつ違う。
この映画にはそれほどたくさんのロケーションが出てくるわけではありませんが、いくつかの場所を繰り返し訪れることで、観客にとってもその場所が少しずつ親しみの感じられる場所になっていくのではないでしょうか。
自らの罪を隠そうとしながらも、欲望を隠そうとはしないジェレミーとともに進んできたはずの物語は、その中盤において大きな転換点を迎えるように見える。そこから先では、隠すべき罪とそうする必要のない健康な欲望の間に、さほどの違いはないように思えるからだ。フィリップ神父は言う、「誰もが殺戮に加担し、それを自覚している」世の中で、殺人を犯したということにどれほどの意味があるのかと。死ぬよりも愛のために生きろと。きみも私を愛せる、「最初は大変だが大丈夫だ。難しいと思った相手も全員愛してきた」と。
AG 神父はジェレミーがいつか自分を愛せるようになるだろうと言いますが、彼はそう信じたいのだと思います。私にとって彼は、愛する見返りとして愛されることができない、そう望むことができない存在なのです。彼は愛する、しかし誰も彼を愛し返してはくれない。でも彼は、それが起こりうるということを信じたい。言うなれば、彼のジェレミーへの言動にはどこか脅迫めいたところがあります。自由であるためには愛することを学ばねばならない、とでも言うような。とても優しく、思いやりに満ちた脅迫ではありますが。
たしかに神父が願った愛は、彼の元へと返ってはこないかもしれない。しかし、この映画の最後に待ち受けるのは、愛の不在ではない。それは神父が願ったものとは違うかもしれないし、ほんの微かなものに過ぎないかもしれないが、愛の兆しはたしかにある。
AG ええ、もちろんその通りだと思います。そこでは、必ずしもセクシュアルである必要のないなにかが生まれつつある。「一緒に寝る」という言葉には性的な含みがありますが、そうではなくただ文字通りに一緒に寝るというアイディアに、ラストシーンの美しさがあると思います。それは子供が夜目が覚めて親の眠るベッドにもぐりこむようなイメージでもあり、また非常にオイディプス的なイメージでもあります。
余談ですが、ギロディ監督の長編作品はいつも100分前後の長さですよね?そこになにかこだわりはあったりしますか?
AG いや、作品の上映時間については特に意識はしてないよ。うん、でも結局のところ、映画の正しい長さというのは90±5分くらいだと思っていて、『湖の見知らぬ男』は92分くらいだったと思うけど、そのくらいがすっきりしていて好きだ。長い映画をつくりたいとは、正直あまり思わないんだ……。でもそれは次の作品で変わるかもしれない。お楽しみに。
取材・構成:結城秀勇、浅井美咲
2025年3月7日
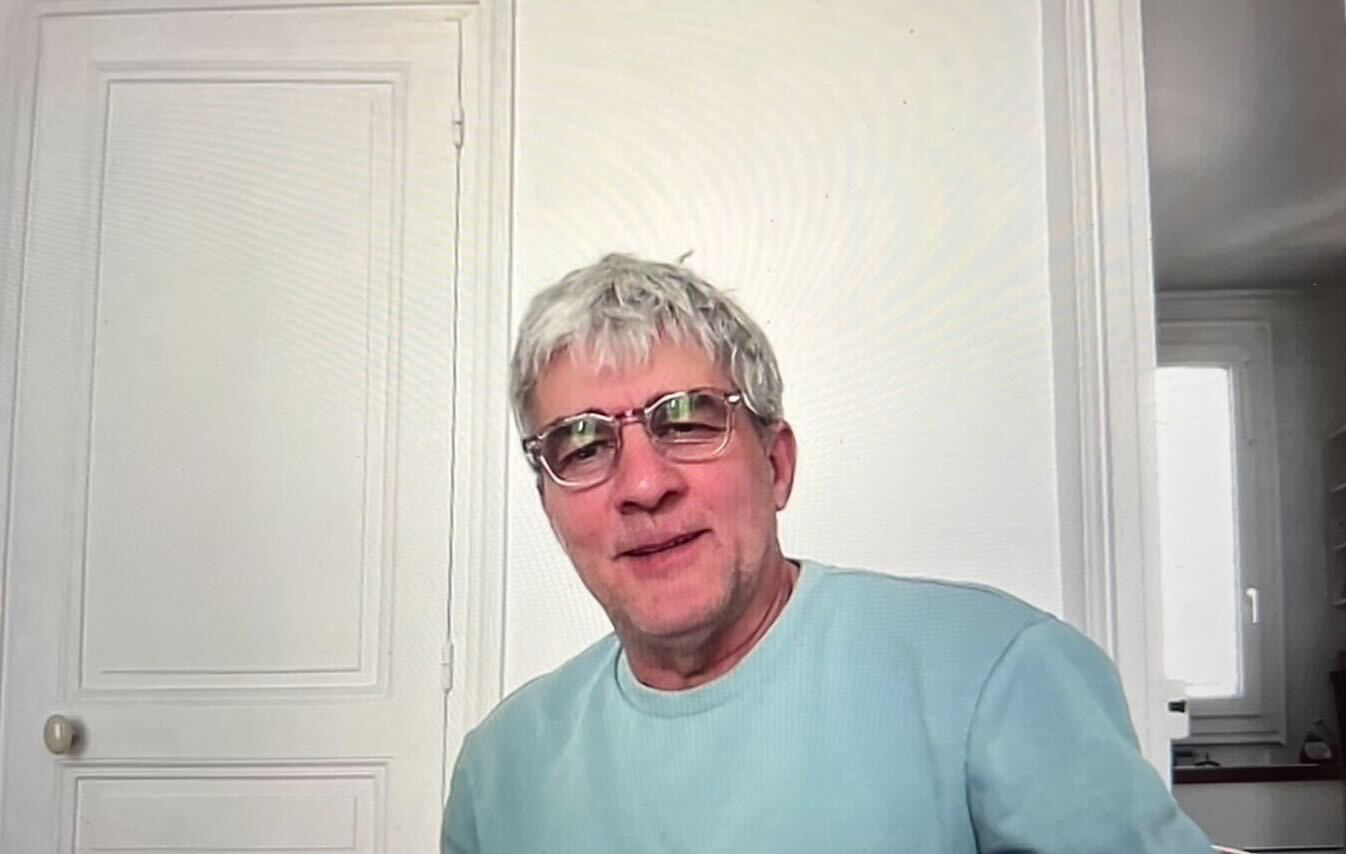
アラン・ギロディ(Alain Guiraudie)
1964年、フランスのアヴェロン県ヴィルフランシュ=ド=ルエルグ生まれ。サスペンスにユーモアを織り交ぜた官能的で独創的な映画が特徴的。これまで、短編3作品、中編2作品、長編7作品を監督している。これまでの主な受賞は、2001年ジャン・ヴィゴ賞、2013年カンヌ国際映画祭「ある視点」部門・監督賞とクィア・パルム賞、2024年ジャン・デリュック賞など。フランスで最も権威のあるカイエ・デュ・シネマ誌の年間ベストテン第1位に2013年と2024年に選出されている。最新作『ミゼリコルディア』は、フランスの劇場公開で、動員23万人を突破し、世界21カ国での公開が決まった。インディペンデント映画としては異例の大ヒットを記録している。


