セックスをしなくても一緒にいることができる
品川悠
このひとにできるだけ近づきたい、しかしそれは叶わない。アラン・ギロディの映画は、少なくとも今回上映される『湖の見知らぬ男』、『ノーバディーズ・ヒーロー』、そして『ミゼリコルディア』の3本は、そのような成就しない(性)愛の物語とひとまず見立てることができる。そう見てゆくと、ギロディ映画において、ひとの行動を突き動かす「欲望」という動因が浮かび上がってくる。彼らは、自らの欲望を隠そうとはしない。つまり、もし本心なるものがあるとしてもそれはどうであれ、各々が自らの欲求を率直に吐露する。
このひとにできるだけ近づきたいという欲望は、あられもなく言ってしまえば、まずセックスをしたいという欲求として描かれる。たとえば、とある湖畔の一夏の出来事を描く『湖の見知らぬ男』において、毎夏そこに通う主人公フランク(ピエール・ドゥラドンシャン)は、初日から気になる男を見つける。気になった男にはいつも相手がいたと惜しむ彼は、だが今回は意中の人ミシェル(クリストフ・ポー)と関係を持つことに、ひとまず成功したように見える。いわゆるハッテン場となっているその湖畔では、誰もが湖で泳ぎ、ほとりで全裸で寝そべり、森の中で身を潜めて性交に耽る。『湖の見知らぬ男』は、相手への接近はおろか、性交までをも容易に実現させてしまう。しかしそれゆえにか、二人は欲望の方向性においてすれ違ってしまう。湖畔の外でもなお関係を持ち続けたいと主張するフランクと、あくまでこの場所の気楽な付き合いに留めようとするミシェル。実際、彼らの性交為は特別な瞬間としてではなく、同じ運動をひたすら繰り返す作業のようにも見えてくる。そしてその性交為を見て愉しむ他の男の存在が、そのような親密さから二人をさらに遠ざける。
ギロディの映画は、主人公の性愛的な欲望をこのように必ず他者のそれと描き重ねることで相対化する。湖畔を訪れたフランクの視線の先には、いつも必ず見返してくる複数の視線が存在していたはずだ。性愛の対象に眼差しを向ける主人公もまた他の誰かによって同じように見られている。
ミシェルとの関係とは対照的に、性愛的な欲望から遠く離れて、フランクはアンリ(パトリック・ダスマサオ)という男性とある種幸福とも言える関係を築いてゆく。二人の会話はしばしば長回しで捉えられ、湖畔に腰掛ける両者の細やかな身振りが記録されてゆくのだが、劇中を通して、二人が向き合うことはない。つねに横並びで捉えられる二人は、互いの距離感を確かめ合いながら言葉を積み重ねる。なんら変哲のないやりとり、その接近ならぬ接近こそが、二人組でいればすぐさま性愛的な関係として短絡されるこの小世界において、むしろ核心に迫るものとなる。そこで、アンリはフランクに忠告していた。「セックスに執着するな」と。

『湖の見知らぬ男』
©2013Les Films du WorsoArte / France Cinéma / M141Productions / Films de Force Majeure
ギロディは欲望が渦巻く(性)愛の物語を、すれ違いの劇として演出する。『湖の見知らぬ男』において、それは初め勃起していた性器がやがて萎えてしまうというかたちで端的に描かれていた。この長編第四作目に示されたのは、要するに、セックスが必ずしも、ミシェルの言葉を借りれば「深い仲」という関係性を保証するわけではないという事態だった。
このように関係が結ばれやすく、また離れやすい湖畔から舞台を多種多様なひとが蠢く都市に移した『ノーバディーズ・ヒーロー』は、独身の中年男性メデリック(ジャン=シャルル・クリシェ)がランニングの最中に偶然出会った娼婦イザドラ(ノエミ・ルヴォウスキー)に一目惚れする場面から幕を開ける。その始まりにおいて示された性愛的な欲望は、しかしこの映画において一貫してその成就を妨げ続けるだろう。まずホテルで、次に教会で、そして彼女の自宅で、ついには自身の家で、性交は必ず闖入者の存在によって阻まれることになる。最後にメデリックは、つねに暴力に晒されるイザドラを救うために、その夫ジェラール(ルノー・ルッタン)に襲いかかるが、彼女が選ぶのは当然と言えば当然だが、路上で偶然出会った男ではなく、30年来付き添っていた夫の方である。
また、その闖入者という存在の中でここでとりわけ重要なのは、その嫉妬深い夫よりも、ホームレスのアラブ人青年セリム(イリエス・カドリ)と仕事仲間の女性フロランス(ドリア・ティリエ)である。彼らもまた同じようにメデリックとの距離をそれぞれのやり方で縮めようとする。セリムは行くあてがないにもかかわらずメデリックのアパルトマンに固執し、フロランスは打ち合わせと称して何とか会おうとするためにしょっちゅう電話をかけてきたり直接家に訪ねてきたりする。しかし、やはりそれらも同様に受け入れられることはない。メデリックは、一方には自らゲイではないと関係を断り、他方にはゲイであると言って関係をいっそう拒絶する。
失恋したセリムは、それでもなお「別にヤラなくても家には泊まれる」とメデリックに伝える。実際、メデリックもイザドラとセックスすることが結局叶わなかったが、束の間の時間を一緒に過ごすことはできた。その際、闖入者として部屋に入ったセリムが、翌朝、二人が着ている服と同じ色を身に纏っていたのは示唆的だ。
映画は、メデリック、同じアパートの住人コック、フロランス、そしてセリムが同じアパートの中に入っていこうとするとき、そこへセリムに好意を寄せる少女が画面に向かって走ってくるショットで幕を閉じる。あらゆる性愛的欲望が達成される瞬間がついぞ訪れなかった『ノーバディーズ・ヒーロー』が示すのは、性愛に固執する限り、誰とも繋がることができないという事態に他ならない。またこれが、イザドラが夫を最後に選ぶ理由をも説明するだろう。
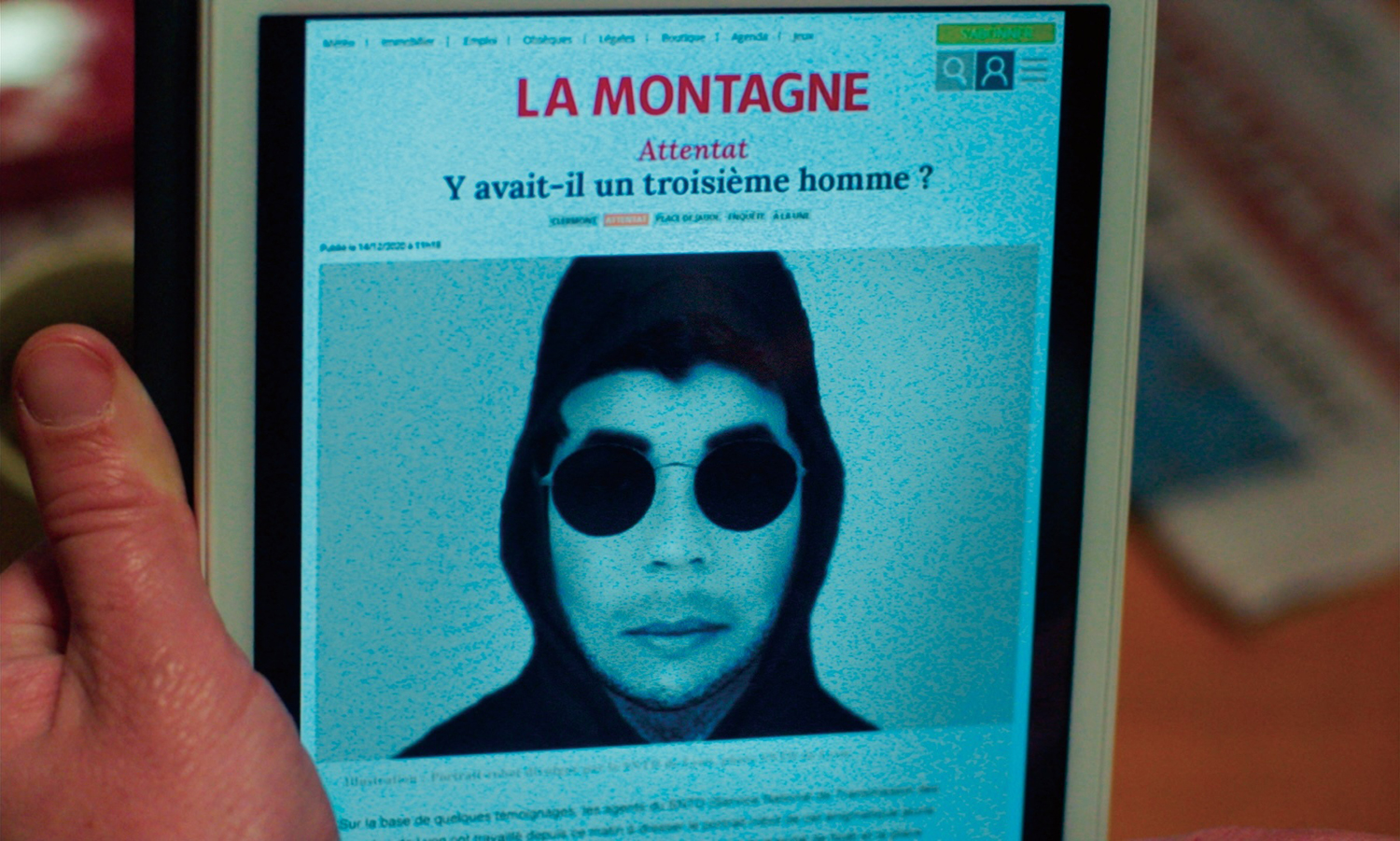
『ノーバディーズ・ヒーロー』
©2021 CG CINÉMA / ARTE FRANCE CINÉMA / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA / UMÉDIA
このような文脈を踏まえて『ミゼリコルディア』に目を向けてみると、この最新作では性交はおろか接吻すらも許されていないかのように見える。とはいえ前二作と比べると、性交為がはっきりと描かれているわけではないにせよ、その欲望の主題とは無縁ではない。
長閑な田舎風景を前身移動で映し出して始まる『ミゼリコルディア』の舞台は、山に囲まれた小さな町である。そこに、本作の主人公ジェレミー(フェリックス・キシル)が数年ぶりに帰郷してくる。その目的は、師事していたパン職人の葬儀に参列するためとすぐに示されるが、のちにその主人を深く想い慕っていたことも明かされる。つまり、実はその始まりにおいて『ノーバディーズ・ヒーロー』とは対照的に、そもそも主人公は欲望の対象を失っていたのだ。ジェレミーは、それからパン職人の妻の家にしばらく居候し、ひさしぶりに訪れた地元の土地を毎日散歩して回ることになる。
ジェレミーが、ワルター(ダビッド・アヤラ)の家に初めて入る序盤の場面では、二人はそこでお酒を飲みながら旧交を温める。生活感が濃厚に漂う空間において、その際、ワルターは暑いからと言って上着を脱ぎ、タンクトップ姿になるとともに、お酒をもっと勧める。この一連の何気ない身振りが、ジェレミーにとって誘惑と映ったのだろうか。ジェレミーはそれを確かめるように、二度目の訪問の際、そのワルターの身ぶりを画面外において反復——服を脱いでワルターのタンクトップにわざわざ着替える——し、そこからさらに進んで、ゆっくりと接近し彼の身体にそっと触れる。しかしワルターはこの振る舞いに対して困惑しつつ、やがて逆上し、ついには彼を家から追い出すことになる。のちにジェレミーは、「お酒を飲むと普段隠されている欲望が表に出てくる」と嘘か本心かにわかに判別しがたい台詞を口にしてなんとか取り繕おうとするだろう。
パン職人の死、ワルターからの拒絶が示すのは、『ミゼリコルディア』における欲望の在り方である。尤もそれは多くのギロディ映画に登場してきた人たちと同様に欲望がそれぞれ成就することはないのだが、この事態が序盤に配されているところに前二作にはない本作の特徴がある。つまり、ジェレミーは、早々に二重に挫折を経験することで、その欲望を持て余すことになる。このことは同時に、ジェレミーの歩行が、多少なりとも目的意識に支えられた散歩や散策というよりも、欲望の力学から離れた徘徊という印象を強めることになるだろう。さらに言えば、『ノーバディーズ・ヒーロー』が最後に「一緒にいること」を拒否して終わる映画だったことを思えば、『ミゼリコルディア』は拒絶した/された後にも生活が続いてゆき、関係がそれでもなお終わらないことをより一層示すことになるだろう。
『ミゼリコルディア』においてもまた逆に主人公を性的に欲望する人物がやはり登場する。フィリップ神父(ジャック・ドゥヴレ)である。パン職人の葬儀を取り仕切った彼は、たびたびジェレミーの前にすっと出現する。偶然を装って遭遇すべく計算の上で動いていたとのちに告白するフィリップ神父は、密かにジェレミーを愛していたのだった。無論、彼の愛も自身が望むようなかたちで成就することはない。
フィリップ神父がジェレミーに愛を告白する崖の場面は感動的だ。町を一望して見下ろせるその崖は、雲が手に届くほど標高が高いように見える。物語中盤で殺人を犯したジェレミーは警察や住人の捜査の追及にもはや耐えきれず、そこから投身自殺を図るためにそこにやってきたのだった。ここでも不意に現れる神父は、その自殺を止めようと試みる。切り返しによって捉えれたこの場面でフィリップは、ジェレミーが犯した殺人が、多くのひとが世界の不幸を見過ごしている罪の重さにおいて五十歩百歩であると主張するのだが、ジェレミーが説得されることはない。そこでフィリップはあらためて告白をする。「自分のために死なないでほしい」。これもあえなく拒絶に遭うのだが、ここでその愛の現実的な妥協点として、神父は「セックスをしなくても一緒にいる」ことを提案する。たまに食事を共にし、たまに散歩する——その積み重ねによって、いずれジェレミーの中に愛が芽生える可能性に賭けるのだ。この場面が感動的なのは、屁理屈とも言える論理まで持ち出してジェレミーに自殺を思い止まらせようとしたからでも、あるいは愛の告白がこの上ない率直さでなされているからでもない。そうではなく、以前二人が言葉を交わした告解室において、翳りを帯びていたジェレミーが、ここで不自然な強い光を受け止めるからではないか。その瞬間、彼は身体をやや神父の方に向け直す。二人が同一フレームに収まるショットを導き、ジェレミーの自殺を止めたようにさえ思えるこの光は一体なんなのか。
崖から町へ戻る際、ジェレミーとフィリップは一瞬手を握って歩く。すぐにほどかれた手は、のちに本作で深い余韻を残すだろう最後の場面に受け継がれる。手を繋ぐ、握るという身ぶりがそもそも相手がいなければできないという単純な事実にここで思い至る。
ただ事態が解決したわけではないし、それ以降も生活は否応なく続く。『湖の見知らぬ男』の中盤、刑事から事情聴取を受ける際、フランクは、殺人事件が起きたにもかかわらず、あたかも何事もなかったかのように依然として振る舞っていられる態度を咎められ、「人生は続きます」という奇妙な返事でもってそれに応える。そう、いずれにせよ人生は続いてしまうのだ。それゆえに、手を握り返すという細やかな身ぶりで締め括る『ミゼリコルディア』は、そのような人生における複雑な欲望のありようをそっと肯定しているように思える。


