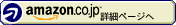『コズモポリス』デイヴィッド・クローネンバーグ代田愛実
[ cinema ]
2台のリムジンがカンヌを湧かせていたのは、ちょうど1年前の今頃のことだろう。『ホーリー・モーターズ』と『コズモポリス』。レオス・カラックスとデビッド・クローネンバーグの、全く似ていないような2人の監督の奇妙な共通項にとても驚かされた。
同名小説をたった6日間で脚本化したというし、台詞はほぼ原作通りだというから、サマンサ・モートンが発する散文詩のような魅惑的な言葉についてもここでは言及する必要は無いだろう。
そんなことよりは、リムジンである。
この狭いのか広いのかよくわからない、乗り物なのかオフィスなのかよくわからない、リムジンという装置。ここには様々な人間が訪れる。訪れるというよりは、現れては消えてゆく、亡霊のようでもある。彼らはいつも言葉を発し、ロバート・パティンソン扮する主人公もそれに応答する、が、彼らはコミュニケーション=対話を成り立たせはしない。誰の言葉も人を動かしはしない。カンバセーション=会話、あるいは"つぶやき"なのである。言葉は積み重ねられて、やがて古びてチリになるのだろう。必要なのは情報だけであり、全ての情報は端末から手に入る。だが主人公は友人の歌手の死すら知らない。おそらく、これは予想に過ぎないが、きっと主人公はこの日、一生でいちばん喋っているのだろう、必要の無い会話を。それゆえ、友人の死を知る事が出来たのだ。
広角レンズでゆがめられた主人公や客人のフレームの外には、常にリムジンの車内がある。窓に映る光景は現実に起こっているようだが、TV中継を眺めているのと変わらない。どうやら「リムジン外」はフレーム内に影響を与えないらしい。ということは、リムジンは動いていてもいなくても同じであるから、自動車ではないのかもしれない。そう、リムジンは自動車ではない。だから、床屋へ行くという目的は果たせない。「タクシーが好きなの」と美しい妻が言うのは正しいだろう、移動を目的とするならば。リムジンの中で、会話は切り返しショットによって繋がれる。面白い事に、見上げたり見下ろしたり、背(というより臀部)を向けたり隣り合ったり、動き回ったりどっしりかまえたり(サマンサ・モートンの存在感がすごい)、皆それぞれのやり方で主人公およびリムジンに向かっている。トイレがついていることも、もちろん、排泄シーンを入れる事で見せてくれている。こんなにもリムジンの車内を使い尽くしたフィルムはあっただろうか。それだけでも愉快である。そしてこの空間は何のためにあるのだろうかと、いぶかしくなってくる。幾通りものラインを、レヴェルを、強度を、すべて包み込んでいる・・・あるいは、遮断している。
妻に会うためにはリムジンを降りなければならない。車内から妻を見つけたら嬉しそうにすぐにリムジンを降りてしまう所は、唯一の、人間らしい感情表現だ。今まで、フレームとリムジン車内に閉じ込められていたパティンソンが閉鎖空間/抑圧空間から解放される。だが会う度に彼は、妻に何らかの理由で拒絶されて、今度は精神的に抑圧、すなわち去勢されてしまうのだから面白い。(なお、この美しい妻を演じるサラ・ガトンは、『危険なメソッド』でも主人公の妻を演じているが、美しさと優雅さ冷たさと強さをたたえる、とても素敵な女優だ。)しかし主人公が感情を吐露しない所がとても良い。私たち観客は、主人公が"どんな人間か"を知らされる事は無い。ただ彼が揺さぶられている1日を、同じように揺さぶられるだけである。おそらく、リムジンと妻は同じレヴェルにいる。両者との別れは、同時に訪れる。その時が、主人公のレヴェルの降下であり、暗殺者と並ぶ時であり、資本よりも血が流れるときである。最初は血の流れていないロボット(ヴァンパイヤ?笑)のようだった主人公も、夢のようにつぶやいていた床屋に辿り着く頃には、頬を紅潮させて、幼い少年のような怯えや好奇心を持った表情を身につけている。
本来ならば恐ろしい敵である筈の暗殺者より、リムジンのほうがより恐ろしく、不可解で、世界の謎の一部のように浮かび上がってくる。"リムジンは夜、どこへいくのか?"という問いに対して、『ホーリー・モーターズ』ではその回答が得られるが、この作品では、その回答を待つ必要は無いということだ。ただ、その問いが発せられる事が重要なのである。
リムジンが国際都市を代弁する装置として浮かび上がりながらも、俳優(とくに女優)達の存在感は圧倒的で、ともすれば装置ばかりが突出し空虚になってしまう所を、人間の肉感や造形や息づかいがドラマを作っていく。うねりを生むとも言えるだろうか。うねりといえば、ラット集団のムーヴメントも登場していたが、たった1人でパイ投げ男として登場したマチュー・アマルリックは、わざとあのように滑稽に弱々しく描かれたのだろう。大きな思惑と小さな思惑、交錯する筈の無いラインがぶつかり、大きな爆発や小さな爆発が次々に起こっている。宇宙を意味するcosmoを冠する単語、cosmopolisとは、そのような混沌を、大掛かりなアクションではなく、役者と小さな装置で冷静に描いてみせた作品だった。現代のNYのリアルな生命であるバスケットボールの少年達が挿入される配慮にも、好感が持てた。






 Cosmopolis/コズモポリス
Cosmopolis/コズモポリス