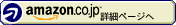『間奏曲』ダグラス ・サーク
結城秀勇
[ cinema ]
8/16、アテネ・フランセ文化センターでの「中原昌也への白紙委任状」のトーク用に調べたことを簡単にメモしておく。
・基礎情報
1. 1957年製作のこの作品は、以後サークのフィルモグラフィとして『翼に賭ける命』『愛する時と死する時』『悲しみは空の彼方に』という傑作群を残すばかりという監督として脂の乗り切った時代の作品にもかかわらず、研究書等でもきちんと触れられることが少なかった。アメリカ本国における本作品の扱いの証左のひとつとしての、 リチャード・ブロディ「『間奏曲』 隠れた傑作」 。
2. 『心のともしび』『悲しみは空の彼方に』とともに、サークがリメイクしたジョン・M・スタール作品のひとつである。リメイク元『最後の抱擁』からの複雑な改変の経緯、及びジョン・ハリデイ『サーク・オン・サーク』において本作の原作がジェイムズ・M・ケイン『セレナーデ』とされている誤解について、詳細に論じた文章、 トム・ライアン「翻案とリメイク: スタール『最後の抱擁』からサーク『間奏曲』まで」
3. 『愛する時と死する時』とともに、サークが故国ドイツでロケをしたハリウッド期の2作品のうちのひとつ。本作製作時の過密スケジュールについて『サーク・オン・サーク』で触れられており、また主人公が「観光客」のような立場をとる本作の物語もあって、さほど「ホームグラウンド」に帰ってきた感は感じられない作品ではあるが(加えて『サーク・オン・サーク』でしきりに語られる戦後西ドイツ(と東ドイツの双方)への居心地の悪さもまた関係しているのかもしれない)。
・物語
ケインの原作では(及びスタール『最後の抱擁』でもギリギリ)労働運動に関わる人物であったはずの主人公だが、『間奏曲』のヘレン(ジューン・アリソン)は就職した瞬間から上司や周囲の人間に、「どうせワシントンからミュンヘンに新しい恋を探しにきたんでしょう」呼ばわりを受ける。その場では「仕事しにきたんです」と否定するヘレンだが、中盤以降は仕事サボってデートしてばかり。
ヘレンを巡る恋愛の四角関係の登場人物たち。ヘレンを取り合うことになる、指揮者トニオ(ロッサノ・ブラッツィ)とアメリカ人医師モーリー(キース・アンデス)は、その見かけにおける「ロマンティシズムvs現実主義」「不倫vs結婚」という構図にもかかわらず、職業としての音楽家=ロマン、医者=現実という区別とは本質的にはさほど関係がない。舞台袖で見た指揮者トニオの姿にヘレンが魅了されるのと同等に、彼女は診察中のモーリーの姿にもまた魅了される(そして将来「ミュンヘン帰りの開業医」になる人物を選ぶのが「現実的」なのか、という問題もある。それはそれで十分「シンデレラストーリー」じゃないかと)。
観客にはあらかじめ知らされていながら、ヘレンは直接遭遇するまで気づかないトニオの妻レニ(マリアネ・コッホ)の存在。しかし観客に対してすら、執拗にグランドピアノの天板に映り込む幻影として提示され続ける彼女の本質的な亡霊性。
・PCを超えて
『悲しみは空の彼方に』の人種問題、『天が許し給うすべて』のジェンダー格差階級格差、『間奏曲』の(マイルドな)階級格差という見かけにかかわらず、サーク作品においてこれらの問題は、政治的な正しさによって解決可能な二者択一ではない。たとえ黒人を同じ人間として扱おうとも白人が「人生の模倣」から抜け出ることができるわけではなく、女性の年齢といったルッキズムや男権主義社会に抵抗したところで資本主義社会の外に抜け出ることが可能になるわけでもない。
サーク作品の主人公たちの決断はしばしば「これ以外に道はない」というかたちをとる。それがみんな幸せになるハリウッドエンディングとなるか、そうならないのかは、本質的には彼/彼女らの選択とまったく関係がない。それを「天が許し給う」かどうかは監督の埒外にあることは『サーク・オン・サーク』で繰り返し語られる通りである(すべてはスタジオの思し召し通り)。
そうした意味でサーク作品の目指すところは、最終的なハッピー/アンハッピー・エンドとという結末にはない。最終的になにがどちらに転ぶのかわからないロッタリー的エンディングに導くほどまでに、登場人物たちの希望の可能性を消尽させる運びこそが、サーク作品の本質である。つまり『サーク・オン・サーク』でサークが好むと語る、「挫折」と「八方ふさがり」の状況をいかにつくりだすかということだ。それは多くのハリウッド映画とは異なり、選択を間違ったことによって起こるのではない。いかなる道を通ろうが、どんな選択を経ようが、それは決して避けることができないのだということを示すためだけに、登場人物たちの決断は積み重ねられる。『悲しみは空の彼方に』のエンディングについて、おそらくこの物語の後、結局は各登場人物がめいめいに自分たちの「循環」へと帰っていくのだろうと(いささかペシミスティックに)述べた後、サークはこう付け加える。
「でも要は、こんなことしてちゃいけないってことなんですよ」
・we have no choice, it's impossible
『間奏曲』のラストでヘレンが口にする「他に道はないの」は、上記の極めて典型的な例である。繰り返しになるがこの言葉は、他に道がないけどこの道なら大丈夫だ、ということを意味するのではない。「他に道がない」この道も、また破滅にいたる道に他ならないことを宣言する言葉なのである。ではそうならないための方法があったのか。一瞬だけ「出口=way out」が見えた、と彼女は口にする。それはひらたく言って、もうすでに亡霊のようにしか生きていけない女性を改めて殺す、ということである。さらにはそれを敷衍すれば、ヘレンの欲望を完全に充足させる唯一の方法とは、トニオの湖畔の別荘が大雨によって世界から孤立した場所となった晩に彼女が口にするように、「世界にふたりだけだったらいい」ような世界の到来、つまり完全なる人類の殺戮によってでしかない。レニのことは気にせずに自分が好きなようにすればいい、「レニなんて存在しない」(!)という、レニの叔母である伯爵夫人から謎のお墨付きをいただいたヘレンが、それでもトニオを選ぶことができない最大の理由はそこにある。『間奏曲』とは、「愛する時と死する時」ならぬ「愛する時と殺戮する時」という、二者択一ではない不可分の時間を同時に生きることなのだ。
上記を踏まえて『間奏曲』を改めて見直せば、この映画の画面の片隅に「出口=Ausgang」という表示が異様なまでの頻度で映り込んでいることに戦慄するだろう。トニオ=フェアリーテイルへの逃避かモーリー=「ぼくらはいつももどってきてしまう」資本主義的再生産かという見かけ上の対立の水面下で、絶えず殺戮と排除という「出口」がいくつもぽっかりと口を開けている。にもかかわらず、「小市民的なアメリカ人女性のつかの間の恋」という凡庸な外見のままで最初から最後まで駆け抜けてしまうこの作品は、控えめに言っても奇跡的だ。
アテネ・フランセ文化センター「中原昌也への白紙委任状」にて上映
 Amazon.co.jp | ダグラス・サーク Blu-ray BOX (『天はすべて許し給う』『間奏曲』『悲しみは空の彼方に』収録) DVD・ブルーレイ - ジェーン・ワイマン, ロック・ハドソン, ラナ・ターナー, サンドラ・ディー, ジューン・アリソン, ロッサノ・ブラッツィ, ダグラス・サーク
Amazon.co.jp | ダグラス・サーク Blu-ray BOX (『天はすべて許し給う』『間奏曲』『悲しみは空の彼方に』収録) DVD・ブルーレイ - ジェーン・ワイマン, ロック・ハドソン, ラナ・ターナー, サンドラ・ディー, ジューン・アリソン, ロッサノ・ブラッツィ, ダグラス・サーク
ジェーン・ワイマン出演ロック・ハドソン出演ダグラス・サーク監督
¥11,249