第32回マルセイユ国際映画祭、FID 報告ーーカンヌからマルセイユへーー
槻舘南菜子
[ cinema ]
7月19日から25日にかけて、マルセイユ国際映画祭FIDが開催された。昨年から今年にかけて、多くの映画祭が中止、あるいはオンライン開催を余儀なくされたにも関わらず、FIDは2020年度も開催された稀な映画祭の一つだ。通常は7月初旬を会期としているが、今年度は、パンデミックの影響で時期をずらしたカンヌに合わせ、その直後へ日程変更される形となった。ディレクター、ジャン=ピエール・レム氏が指揮を執るFIDのプログラムは、カンヌとは真逆の先鋭性と仏映画産業に媚びない強い芸術的志向を持っている。他仏の中規模国際映画祭では、仏国内での作品配給に追随する、あるいは、フランス映画のセレクション以外は他国の国際映画祭(ロッテルダム、ベルリン、ロカルノなど)ですでにノミネートした作品の仏プレミアが多くを占める一方で、FIDは「発見」という映画祭本来の役割を軸に据え、ワールドプレミアへの強いこだわりを掲げる稀有な映画祭だ。ジャンルの垣根を越えた、フィクション、ドキュメンタリー、実験映画など幅広いセレクションもまた、特徴の一つでもある。だが、FIDは映画祭としての強烈とも言える個性によって、映画作家を孤高の芸術に閉じ込めるわけではなく、新たな才能をカンヌ国際映画祭などの大規模な映画祭に送り出してもいる。たとえば、今年カンヌ国際映画祭で審査員を務めたマティ・ディオップ監督は、中編『Mille soleils』(2013)でFIDのグランプリを獲得後、処女長編『アトランティック』(2019) はカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、パルムドールに次ぐグランプリを受賞した。このことからも、FIDとはある種開かれた砦のような国際映画祭だと言えるだろう。そして、カンヌ国際映画祭コンペティション部門の監督賞を受賞したばかりのアピチャートポン・ウィーラセータクン。今年のFIDでは新作『Memoria』の凱旋上映とともに、キャリア全体を展望するマスタークラスとレトロスペクティブが開催され、名誉賞を授与されることとなった。実験性とドキュメンタリーを融合させ、モノクロで撮影された処女長編『真昼の不思議な物体』(2000)を皮切りに、長編二作目『ブリスフリー・ユアーズ』(2002)では、カンヌ国際映画祭の併行部門を経ずに公式のある視点部門にノミネートされる。『トロピカル・マラディ』(2004)で同映画祭の公式コンペティション部門にノミネート後、『ブンミおじさんの森』(2010)では、最高賞のパルムドールを受賞するなど、驚くべき国際的な活躍を遂げている。ある種、FID的な先鋭性を出発点とし、国際的なキャリアを積みあげた作家だと言えるだろう。
今年の国際コンペティション部門に選出された14本の作品中、仏&仏共同製作作品は3本のみで、製作国はもちろん、尺、主題やスタイル、ジャンルもまったく異なるため、今回も真正の多様性を持ったセレクションとなった。その中でも、ジョルジュ・バタイユの幼少期に想像を巡らせた、Antoni Collot監督『Jojo』は、陰影の中に浮かび上がる俳優たちの顔と身体性の強さを感じる作品であり、とりわけ、映画に初主演した俳優 Attila Meste de Segonzacは、大きな発見と言えるだろう。

Antoni Collot『Jojo』
また、すでにベルリン国際映画祭のフォーラム部門で、『Short Stay』(2016)『Classical Period』(2018) で注目された、Ted Fendt監督の新作『Outside noise』は、期待を裏切らない秀作だった。職業俳優ではない友人たちを起用し、監督本人も出演しながら、彼らとともに脚本を共同執筆するミニマムなスタイルで、ベルリンとウィーンの街を背景に三人の女性の他愛もない会話と街の雑踏を淡々と切り取っていく。彼の徹底的に細部にこだわる演出は健在だ。

Ted Fendt『Outside noise』
さらに、Declan Clarke監督『Saturn and Beyond』の始まりは、FIDのセレクションにも多く見られる映像の造形的な魅力に止まるオブジェのように思えたが、科学映画的な映像に、時折差し込まれる監督自身の記憶と記録の混在ーー最終的には父親の死が現前するーーは、その造形的な美学との温度差によって、感情的に我々を動揺させる美しい作品だった。
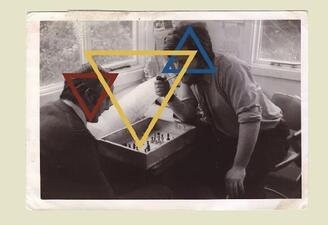
Declan Clarke『Saturn and Beyond』
 日本からは、杉田協士監督『春原さんのうた』がノミネートし、グランプリ、俳優賞(主演女優、荒木知佳氏)、観客賞、三冠を受賞し、アジア映画として、映画祭始まって以来の快挙を成し遂げた。日本映画としては、マルセイユ国際映画祭史上初のグランプリ受賞となる。『春原さんのうた』は、『ひとつの歌』、『ひかりの歌』から一貫した「喪失と共に生きること」を描いている。杉田監督は、実際の私たちの人生においてそうであるように目の前にいる誰かの全てを知ることは到底できないという当然の事実を、距離を取ったカメラの、だが穏やかな眼差しを持って捉える。作家であり歌人の東直子による第一歌集『春原さんのリコーダー』の表題歌「転居先不明の判を見つめつつ春原さんの吹くリコーダー」を原作としていることからもわかるように、私たちは、多くの余白を読むことを必要とされるように感じるだろう。だが、登場人物の関係性や物語の伏線、出来事の示す明確な意味は、すぐには、あるいは、まったく見えてこない。登場人物の感情や彼らの持つ背景は一切説明されず、独特のリズムを持って切り取られた親密な空間の中を、登場人物たちは、横切るか、止まるかを選択する。そこに明瞭な理由や動機は見えず、過ぎていく時間の流れの中で、多くの謎は謎のままとり残されていくのだ。しかしながら、杉田監督の眼差しは、他者の持つ痛みや静かに存在する感情の欠片を置き去りにはしない。フレームの中に生起する出来事、その細部に目を凝らす、耳を澄ませることで、決して理解に至らなくとも、誰かを思い、考え続けること、寄り添うことが可能なのだと語っているのだ。『春原さんのうた』は、マルセイユ国際映画祭FIDで、「謎と驚きに満ちた、今までかつてない新しい日本映画」として高い評価を受けたが、日本映画という枠に留まらない既存の映画の持つ文法を凌駕する「新しい」映画として、記憶に残ることだろう。
日本からは、杉田協士監督『春原さんのうた』がノミネートし、グランプリ、俳優賞(主演女優、荒木知佳氏)、観客賞、三冠を受賞し、アジア映画として、映画祭始まって以来の快挙を成し遂げた。日本映画としては、マルセイユ国際映画祭史上初のグランプリ受賞となる。『春原さんのうた』は、『ひとつの歌』、『ひかりの歌』から一貫した「喪失と共に生きること」を描いている。杉田監督は、実際の私たちの人生においてそうであるように目の前にいる誰かの全てを知ることは到底できないという当然の事実を、距離を取ったカメラの、だが穏やかな眼差しを持って捉える。作家であり歌人の東直子による第一歌集『春原さんのリコーダー』の表題歌「転居先不明の判を見つめつつ春原さんの吹くリコーダー」を原作としていることからもわかるように、私たちは、多くの余白を読むことを必要とされるように感じるだろう。だが、登場人物の関係性や物語の伏線、出来事の示す明確な意味は、すぐには、あるいは、まったく見えてこない。登場人物の感情や彼らの持つ背景は一切説明されず、独特のリズムを持って切り取られた親密な空間の中を、登場人物たちは、横切るか、止まるかを選択する。そこに明瞭な理由や動機は見えず、過ぎていく時間の流れの中で、多くの謎は謎のままとり残されていくのだ。しかしながら、杉田監督の眼差しは、他者の持つ痛みや静かに存在する感情の欠片を置き去りにはしない。フレームの中に生起する出来事、その細部に目を凝らす、耳を澄ませることで、決して理解に至らなくとも、誰かを思い、考え続けること、寄り添うことが可能なのだと語っているのだ。『春原さんのうた』は、マルセイユ国際映画祭FIDで、「謎と驚きに満ちた、今までかつてない新しい日本映画」として高い評価を受けたが、日本映画という枠に留まらない既存の映画の持つ文法を凌駕する「新しい」映画として、記憶に残ることだろう。

『春原さんのうた』は2022年よりポレポレ東中野ほかで公開予定
海外映画祭用予告編はこちらから


