『プロミス』ジャスティーン・シャビロ、B.Z.ゴールドバーグ
金在源
[ cinema ]
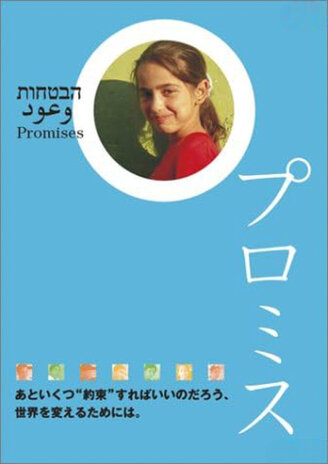 イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区への侵攻が始まって1年が経過した。ガザ地区での死者は4万人を超え、侵略と虐殺が止まる気配はない。イスラエルとパレスチナの問題はこの1年間で始まったものではない。2001年に制作されたドキュメンタリー映画『プロミス』はイスラエル、パレスチナの双方に住む人々の暮らしや生活環境、そして彼らの思想を形成している歴史を学ぶうえでも重要な作品である。そして、制作から20年が経過した今、この作品を鑑賞することの意味を考えたい。
イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区への侵攻が始まって1年が経過した。ガザ地区での死者は4万人を超え、侵略と虐殺が止まる気配はない。イスラエルとパレスチナの問題はこの1年間で始まったものではない。2001年に制作されたドキュメンタリー映画『プロミス』はイスラエル、パレスチナの双方に住む人々の暮らしや生活環境、そして彼らの思想を形成している歴史を学ぶうえでも重要な作品である。そして、制作から20年が経過した今、この作品を鑑賞することの意味を考えたい。
本作は第二次インティファーダが起こる前の1997年から2000年にかけて、イスラエルとパレスチナの7人の子どもたちを追った作品となっている。前半は双方の子どもたちの日常生活とインタビューからなっており、後半ではユダヤ人の双子がパレスチナ難民キャンプを訪れ、パレスチナの子どもたちと交流する姿が記録されている。
7人の子どもたちは多様なバックグラウンドを持っている。友人をイスラエル兵に殺されたファラジ、父親がイスラエルの刑務所に拘留されているサナベル、ハマスを支持しているマハムードがパレスチナ側に住む子どもとして登場する。一方、イスラエル側に住む子どもは、ホロコーストを生き延びた祖父を持つ双子のヤルコとダニエル、ユダヤ人入植地であるベイト・エルに住むモイセ、ラビ(ユダヤ教の聖職者)になる勉強をしているシュロモの4人である。
前半のインタビューでは、子どもたちが生活環境や親からの教育を通して抱くようになった思想や敵対心、融和の可能性を語る。ほとんどの子どもたちが相手を追い出し、殺すことにためらいはないと発言する中、「アラブ人を追い出そうとするのは間違っている」と語る双子のヤルコとダニエルは印象的だ。西エルサレムのパレスチナ人地区に住む彼らにはホロコーストを生き延びたポーランド移民の祖父がいる。二人から「神を信じているか?」と聞かれた祖父は口ごもる。孫たちの質問をなんとかはぐらかそうとしながら「もし神がおじいちゃんを見守ってくれてたらあんなひどい目に遭わずに済んだろう」と小さく語る。そんな祖父の経験を知る二人はイスラエルとパレスチナの問題に対して「戦争で国を奪い取ったのは僕たちの方なんだ」と自分たちの持つ加害性を子どもたちの中で唯一言葉にする。そして彼らは、監督のB.Z.ゴールドバーグからパレスチナの子どもたちの話を聞きながら、次第に直接話をしてみたいと興味を抱くようになる。
ヨルダン川西岸地区のデヘイシャ難民キャンプに居住するファラジという少年は、親友をイスラエル兵に殺され、その仇をいつか取りたいと願っている。イスラエルの子どもたちとは絶対に会いたくないと言っていたファラジも、友人と話し合い、監督からヤルコとダニエルの話を聞くうちに彼らのことを知りたいと思うようになる。ファラジは監督の携帯電話を使ってヤルコとダニエルに電話をかける。お互いつたない英語を使って自分たちの近況を話し、直接会って話したいと思うようになる。そして、検問を通過できないファラジのためにヤルコとダニエルが彼の住む難民キャンプに訪れることを決意し、1日だけの交流が実現する。ヤルコ、ダニエル、ファラジを含めた難民キャンプに暮らす子どもたちは英語を使いながら会話し、一緒にゲームやサッカーをして遊び、食事を共にする。その後、テーブルを囲み1日を過ごしてみてお互いのことをどう思ったか語り合う。相手の境遇を知って「ちゃんと話をすればお互いのことを理解できる」と肌で感じた子どもたちの言葉がこの出会いの意味を物語っている。当初はイスラエルの子どもと交流することに抵抗感を抱いていたファラジは泣き出してしまう。なぜ泣いているのかを聞くと、子どもたちの間を取り持ってくれた監督のB.Z.ゴールドバーグがアメリカへ帰ってしまうと自分たちはもう会うことができない、せっかくいい友達になれたのに私たちは友達になれたことを忘れていってしまうとしゃくりあげながら吐露していく。お互い20分程度の距離に住みながら、友達ともう二度と会えなくなる現実の残酷さを嘆く子どもたちの姿を見ていると、こちらも胸を締め付けられる思いがした。
本作を配信している「アジアンドキュメンタリーズ」のページには「最終的な和平の可能性は、パレスチナとイスラエルの子ども達に託されます」という記載がある。本作の発表から23年が経った今、彼ら彼女らは生きているのだろうかと私は考えてしまう。パレスチナへの侵攻が続く今、この作品でお互いに出会い「私たちは理解し合える」という思いを抱いた子どもたちは、大人になった現在その思いを抱えたまま相手を殺し、自分の命が奪われる恐怖を生きていることになるのではないか
「和平」の名のもとに大人が子どもたちを出会わせ、当時は彼ら彼女らにとって希望として見えていたものが、今では呪いとなっているのではないかと私は思ってしまった。
作中、アラブ人との交流を拒否し続け、射撃訓練をしているイスラエル兵の姿を見て「もし的を間違えて撃ったとしてもアラブ人に当たるだけだから問題ない」と語っていたモイセは、2年後のインタビューで以下のように語る。
「ユダヤ人とアラブ人が向き合わないことには平和はやってこない。でも僕自身がアラブ人と話し合うことはない。彼らと直接交渉すべき人は別にいる。30歳以上の大人や、大臣をはじめとする政治家たちだ」
彼が言うように、平和を実現していかなければならない責任を担っているのは子どもではなく大人である。私たちが子どもたちに託すべきは「和平の可能性」ではなく、「平和な世界」ではないか。それを実現しないまま、子どもたちに託すという行為は、大人がその責任から逃げようとしているだけのように見える。この作品に登場する子どもたちは、今生きているなら30歳前後になっていることになる。世界はイスラエルとパレスチナが抱える問題を解決できないまま、彼ら彼女らを大人にしてしまった。上の世代が解決できなかった課題を次の世代に押し付け続けることは終わりにしなければならない。それは日本に住む私たちの課題でもある。日本に住む私たちもこの世界を構成する大人として、パレスチナで起きている虐殺を止め平和を実現していくための行動が今求められているのではないだろうか。
【関連記事】


