6/16(水)
「一本の映画を作ることは人間同志による冒険である」
オリヴィエ・ペールがブリュノ・デュモン監督、そして彼の映画製作を長年支えてきたプロデューサーのジャン・ブレアとランチ・ミーティングを行うというので、監督にも久々にお会いしたく、参加させてもらう。デュモン監督はこれまでに2回ほど特集を開催し、日本にお迎えしていて、最後は2015年、その当時の最新作『プティ・カンカン』(*1)を含めたほぼ全長編作、そして彼がもっとも敬愛する映画作家のひとりジャン・エプシュテインの特集を「カイエ・デュ・シネマ週間」の枠で開催させてもらった。大阪、京都、東京と、各会場でティーチインを行い、撮影、俳優とのやり取りについての具体的なエピソードのほか、各作品のテーマついて深遠かつ明晰な言葉で丁寧に語ってくれた。アーティストというのは、えてして他のアーティストの作品について語る時の方が、自分の創作の核心に触れるもので、デュモン監督も、エプシュテインについて語っていた時の方がまっすぐにその映画への情熱を吐露されていたように感じた。一見、物静かで、厳格そうに見えながら、その場、そこにいる人たちの中に自分のペースで入っていき、自然と馴染んでいくその姿を見ながら、監督の作品に登場する物静かな人々や風景が、突如ざわざわとノイズを発し始め、殺風景に見えていた場所がとてつもない表情、出来事性を纏い始める世界への眼差しの在処をひそかに探していた。観光にはほとんど興味がなかったが、京都で唯一訪れたいと言われたのが満願寺の溝口健二の碑だった。ひっそりと建っているその石碑の前にしばらくの間佇み、言葉を発することなく、その場を立ち去っていく監督の一瞬の目配せを受け、はっとして、そそくさと後を追った。
バスティーユ広場に面したカフェのテラスはランチ時で多くの人たちで賑わっており、日常が徐々に戻りつつあるのを感じる。デュモン監督は6年前の巡業を覚えていてくれて、いい旅だったよ、とひと言、笑顔を浮かべて述べてくれた。レア・セドゥ主演の最新作『フランス』がカンヌ映画祭コンペでお披露目ということで、ポスターのデザインなど広報について確認しながら、主演であるレアとの仕事がいかに充実したものだったか、作品への満足感、幸福に満ちた言葉を耳にし、同作品への期待が高まる。

ブリュノ・デュモン
その『フランス』も共同製作しているオリヴィエ・ペール率いるアルテ・フランス・シネマは、年に20数本の長編フィクション作品、ドキュメンタリー作品1本、アニメーション作品1本、合計22本の製作を支援している。まずはディレクターであるオリヴィエと彼のスタッフによって応募された脚本が読まれ、そこで最初のセレクションが行われ、その後、アルテのスタッフと、外部から選ばれた人々と半々で構成される10名ほどの選考委員会によって話し合われ、支援する作品が決定する。ちなみに現在の外部からの選考委員は、元カンヌ国際映画祭前会長のジル・ジャコブから、若手映画監督のジュスティーヌ・トリエ(『ソルフェリーノの戦い』、『ヴィクトリア』)やニコラ・パリゼール(『アリスと市長』)、その他、配給会社、セールス会社の人々で構成されている。各々の脚本、キャスティングから見えてくるその企画の意図、その(技術的、商業的な)実現性、あるいは現代映画における革新性、新人でなければこれまでのその監督のフィルモグラフィー内での位置づけ、その他いろいろな観点から自由に意見を交し合い、時間をかけ、丁寧に検討していく。この日のランチでもデュモン監督の次回作についても触れられていた(どうやらSF映画であり、『プティカンカン』以来、作風、ジャンルを果敢に挑戦してきたこの監督の新境地がまた見られそうだ)。監督、プロデューサー、映画史家、映画祭プログラマー、批評家、配給関係者、それぞれ立場の異なる映画関係者たちが、批評的視座を持ち、今作られるべき、生まれるべき映画作品はどんな作品なのか議論し合う(万が一、自分の所属している団体、グループに寄りすぎた発言、意見が目立つ場合は退いてもらうとのこと)。そこからフランスだけではなく、世界中の映画作家たちに創造の可能性が開かれ、支援が決定された後も、製作中の監督やプロデュサーたちとのやり取り、劇場公開時、その後のテレビでの放送、ソフト発売まで、作品を支えていく。こうしてひとりの作家の創造の可能性を開き、時にアドバイスをしながら、作品が観客に届くまで寄り添い、参加していく仕事に喜びと誇りを感じているというオリヴィエ・ペールは、かつてロカルノ国際映画祭のディレクターを務めていた際に、同映画祭で特集を組み、大好きな監督のひとりであるというヴィンセント・ミネリの『バンド・ワゴン』(1953)を挙げながら、映画作りについてあるインタビューで次のように述べていた。
この映画で好きなのは、インディペンデントで、それぞれ異なる資質、キャラクターを持った人々が集まって、資金を集めて、ショーを行おうとしている姿が描かれているところで、映画を作ることも同じで、成功するかどうか分からないながらも、人々が一緒になって働き、資金を集めていく。 今日、良い映画を作るためには、そのことを忘れてはいけない。つまりもっとも重要なのは、自分が好きで、一緒に仕事をしたいと思う人たちと共に集まること、それは家族のようなものであり、多くのお金を得られなくても、芸術的な自由を持ち続けることだ。 映画作りは人間同志による冒険であり、それは非常に人間的な体験だ。とても長く、厳しいプロセスを要するからこそ、好きな人たちと一緒に作ることが大切だ。 勇気を持って映画を作っている若い人たちを心から尊敬している。20年前、40年前よりもずっと難しくなった映画作りを、今日でも行おうとしている人々を私は本当に尊敬していて、サポートし、成功する機会を与えたいと思っている。(オリヴィエ・ペール)
(*1)『プティ・カンカン』は現在、映画配信サービスJAIHOにて配信中
「途方もない何かを信じること」
バスティーユからパリ18区のクリシー広場、その近くの路地にあるアートセンター 、ル・バル(LE BAL)で開催中の「ワン・ビン展」へ向かう。賑やかな広場を抜け、坂になっているアンパス(袋小路、行き止まりになっている通り)を上がるとすぐに緑に囲まれ、ゆったりと落ち着いた佇まいのル・バルのカフェのテラスが見えてきて、一気に、異次元へと誘われていく。ル・バルは写真、ビデオ、映画、ニューメディアに焦点を当てたアートセンターで、展覧会、講演会や討論会が開催されるほか、本の出版・販売も行っていて、パリに来ると一度は訪れたい場所のひとつだ。場所の歴史も興味深く、もともとは第一次大戦後、世界大恐慌が勃発するまでの1920年代、いわゆる「Les Années Folles 狂乱の時代」に賑わったキャバレー、ダンスホールであり、第二次世界大戦後、1992年まではフランス最大の場外馬券発売公社だったとか。その後しばらく放置されていたところ、2006年にレイモン・ドゥパルドンほかマグナム愛好家協会により、ル・バルを立ち上げる企画が生まれる。ダンスホール時代の天井や柱をいかして改築されたのち、2010年9月にオープン。ディレクターにはマグラムフォトのヨーロッパディレクターを務めていたディアンヌ・デュフールが就任し、「ワン・ビン展」はドミニク・パイーニと彼女がキューレーションを担当している。展示スペースは約350㎡あり、1階、地下と2つのフロアに分かれている。ブックショップを通り、1階の展示スペースへと入っていくと、待ち合わせをしていたパイーニ氏の姿が見え、すでに展覧会についてゲストたちに解説を始めていた。これまでもシネマテーク・フランセーズでドミニクが手がけた展覧会、アンリ・ラングロワ展、ミケランジェロ・アントニオーニ展など、彼の解説、ガイド付きで鑑賞する幸運に何度か恵まれてきたのだが、一つひとつの展示を説明するというよりも、まずは全体の構成、セノグラフィー(空間演出)をダイナミックに説明してくれ、その中を進んでいくための道標を示してくれる。ワン・ビンを『鉄西区』(2003)のフランス公開以来、擁護し、対話を続けてきたドミニクは、このアーティストの展覧会を現在開催する意義について次のように語ってくれた。
既成概念や先入観がまったくないという感覚を与えてくれるドキュメンタリー作家は、私にとってワン・ビン以外にはいない。ワン・ビンは『リュミエール主義者』であり、『ロッセリーニ主義者』である。つまり彼は現実に何かを押しつけることなく、そこから感情が生まれるかもしれない、あるいはそこから何かを知り得るかもしれないという可能性だけを信じている。彼の映画は、私たちの代わりに考えようとなどしない。しかも、ドキュメンタリー作家でありながら、美しさを恐れず、それに対して罪悪感も持っていない。ブレヒトが言ったように、美学的に正しいからこそ、政治的にも正しいことができるのだ。その意味で、彼の映画は、中国はもちろんのこと、それを越えて、世界について私たちに語りかけてくる。シャンタル・アケルマンや、ガス・ヴァン・サントを彷彿とさせるような芸術的なジェスチャーでね。
ドミニクによると、同展はこの映画作家にとっていずれも本質的な3つのモチーフ、3つの時で構成されている。「破壊」(『鉄西区』)、「収容、幽閉」(『収容病棟』、『苦い銭』、『父と息子たち』)、そして「尾行、追跡」(『名前のない男』)、これらのモチーフをもとに、ワン・ビン自身と共に選ばれた作品の抜粋がループ上映されたインスタレーションへ、それでは進んでいこう。
まずは1階の会場、「破壊」の時へ。日本占領軍が建設した鉄西区にある中国最大の鉄鋼コンビナートの解体を、2年間にわたりDVカメラで撮影した9時間の作品、世界が衝撃と共にこの映画作家を発見することになった叙事詩的なドキュメンタリー『鉄西区』。ひとつのスクリーンにはコンビナートが雪に埋まっていくその風景を押し分けるように進んでいく列車がトラベリングで捉えられ、もうひとつのスクリーンには工場の大浴場に蠢く労働者たちの肉体が煙の中から浮かび上がってくる。仮借なく覆われ、凍結されていく歴史と、すべてを剥ぎ取られ、肉体のみで寄り添い、抵抗し続ける労働者たち、白と赤、2つのスクリーンが並置されている。

「破壊」(『鉄西区』)
そこから少し離れた下の方にもうひとつ、小さめのスクリーンが設置されており、雪の中をひとりの少年が歩いて行く姿が映し出されている。その少年がカメラの方を振り向き、しばらくこちらを見つめ、そして踵を返して、雪の中へと去っていく。「一瞬、私たちの方を振り向きながらも、何もない場所、未来へと進んでいくしかない少年、彼の孤独を見せたかった。それは、この展覧会で出会うことになる幾人もの人々の絶対的な孤独を予告している」。ドミニクは強い口調でそう語った。
地下に降り、まず『収容病棟』(2013年)の抜粋が映し出される幾つもの小さなスクリーンが壁に散りばめられた空間に入っていくと、病院に収容された人々がまさに正気を失うほど歩き回っていて、その廊下の閉塞感に私たちも包み込まれていく。しかし、インスタレーションのスクリーンに映し出されるそれぞれの生の時間を体験していくことで、ワン・ビンが本作でこの精神病院の抽象的かつ抑圧的な構造を示すと同時に、そこに幽閉されている人々が示す逃走線をあらゆる方向に辿っていくのを感じることができる。

「収容、幽閉」(『収容病棟』)
こうしてカメラを向ける人たちそれぞれが示す逃走線を辿りながら、ワン・ビンは形式を固定することなく、出会う人々に導かれながら,彼らの生のリズムと一体になって撮り続けていく。たとえば繊維工場で働く出稼ぎ若い労働者たちを描いた『苦い銭』(2016年)は、登場する人々が次々移動していき、映画はつねに枝分かれしながら、絶対的に自由な構成を持つに至る。
"流れゆくこと"は、今日の普通の中国人の重要なテーマだ。私は、彼らの物語を語るために、カメラのショットや捉える人物をずらしながら、ある被写体から別の被写体へ、焦点を揺らすようにひとつに絞らずに撮影した。(ワン・ビン)
地下の会場の中央には、同展覧会でもっとも大きなスクリーンに、ギャラリーからの依頼で製作され、滅多に上映されることがない1時間37分の『父と息子たち』(2014年)が、同展唯一、全編通してループ上映されている。ワン・ビンは2010年に雲南省の山間部で『三姉妹〜雲南の子』(2012年)の撮影をしていた際に10代の兄弟に出会う。彼らは、仕事を求めて都会に出て行った石材加工の職人である父親の帰りを待ちながらふたりで生活をしていた。それから数年後、ワン・ビンは、四川省で父親と暮らしていた彼らと再会し、約1カ月間、彼らの日常生活を撮影する。父親の出勤、息子たちの起床、昼食、テレビを点けたり消したりする様子、不衛生な一室で過ごしている彼らの日常のささやかな出来事が固定カメラで記録される。非常に親密で、個人的な小さな空間はしかし、普遍性さえ越えて、私たちのもとへと広がってくる。「生の体験 experience of life」だとワン・ビンは述べる。
彼らの生活状況こそカメラに映したかった。現代中国の問題、つまり経済成長に隠れて何百万人もの人々に影響を与えている物質的、精神的貧困を抱えるこのシステムの偽善を明らかにしなければならないと思った。(...)この映画が示しているのは、生の経験だ。彼らの人生は大切だ。彼らの苦しみを黙認すべきではない。彼らの脆弱さを見てほしい。そしてもちろん、彼らの人間としての誇りや強さも。

『父と息子たち』、背後には『名前のない男』のインスタレーション
この旅は、ワン・ビンの歩んできたその軌跡の中でももっとも先鋭的な作品、『名前のない男』(2008年)で締めくくられる。日々、ショットにショットを重ねて、取り憑かれたような執念でワン・ビンが追い続けた言葉を発することもなく、人間の形をしている以外は謎につつまれた、「最後の人」が、洞窟と風に吹かれた平原の間のどこでもない場所をせわしなく動き回っている。
『名前のない男』は、たった一人で、完全に自給自足で暮らしている。現代の物質主義的な中国において、彼の言葉なき静かな存在は、雄弁なる抵抗の行為であり、純粋な状態における存在であるだろう。(ワン・ビン)
物質的にも歴史的にも急速に変容しつつある巨大な国のあらゆる場所に、まるで測量士のように足を運び、そこで出会った人々、そこに辿り着いた彼らの存在を、彼らの身体が生きるその時間を確認する。この展覧会のタイトルとなっている「歩く眼」は、ワン・ビンのそうした映画作家としての特異なアプローチ、その存在=不在を示しているだろう。そしてその映画作家への深い敬愛と理解を持つふたりのキュレーターによって巧みに構成された同展への旅とは、ワン・ビンの映画作りと同様に、意味やメッセージを見出していくよりも、その中に身を置くこと、その時間、それを身体で感じることがまず求められる。そしてそのことによって、私たちから絶えず奪われている歴史に対する突然の、そして瞬間的な認識を得ることができるだろう。
ワン・ビンの作品たちはかつてない、前代未聞の何かを宿していて、それらが記録する(ドキュメント)ものを絶えず越えていく。その途方もない何かを信じるために、まずはワン・ビンの作品たちを見なければならない。一歩下がったり、高いところから見たりするのではなく、その場に留まり、それぞれの状況や、それぞれの身体の持つ政治的な深遠さからゆっくりと表面へ現れてくるものに寄り添いながら。(リュック・シャセル「リベラシオン」)
「ワン・ビン----歩く眼」展
※同展には1000枚のフォトグラムとドミニク・パイーニ、アラン・ベルガラらの論考が収められたカタログが制作されている

ル・バルのカフェで『ワン・ビン 歩く眼』展カタログに献辞を書いてくれているドミニク・パイーニ
ル・バルを出て、ドミニクと共に地下鉄に向かう。6月ながら、パリは真夏の暑さだ。シネマテーク・フランセーズで同展に併せてワン・ビン特集が開催されており、ドミニクは上映前に毎回作品紹介をして、その後、別のホールで開催されている清水宏の作品を毎日、喜びとともに発見しているとのこと。私は、一度宿に戻り、夕方、ナダヴ・ラピドの最新作『HA'BERECH/Ahed's Knee(アヘドの膝)』の試写へと向かう予定だ。
 これまで何度も来日し、「エリック・ロメール特集」、「フランス女優特集」、「シャンソンと映画特集」など、素晴らしいプログラミングと講演を行い、その優れた批評によって、つねに映画の現在、映画史への新たな視点、考察を示してくれるジャン=マルク・ラランヌ。「カイエ・デュ・シネマ」編集長を経て、2003年から現在にいたるまでラランヌ氏が編集長を務める人気カルチャー雑誌「レザンロキュプティーブル」、通称「レザンロック」が5月17日より開催するカンヌ国際映画祭を記念して、映画特集号を組み、同映画祭に出品予定の作品の紹介や、それら作品の監督や俳優のインタビューを掲載している。そこには3月21日に惜しまれて亡くなった青山真治監督へのラランヌ氏の感動的な追悼文も掲載されている(この追悼文はまた追って訳出してお伝えしたい)。
これまで何度も来日し、「エリック・ロメール特集」、「フランス女優特集」、「シャンソンと映画特集」など、素晴らしいプログラミングと講演を行い、その優れた批評によって、つねに映画の現在、映画史への新たな視点、考察を示してくれるジャン=マルク・ラランヌ。「カイエ・デュ・シネマ」編集長を経て、2003年から現在にいたるまでラランヌ氏が編集長を務める人気カルチャー雑誌「レザンロキュプティーブル」、通称「レザンロック」が5月17日より開催するカンヌ国際映画祭を記念して、映画特集号を組み、同映画祭に出品予定の作品の紹介や、それら作品の監督や俳優のインタビューを掲載している。そこには3月21日に惜しまれて亡くなった青山真治監督へのラランヌ氏の感動的な追悼文も掲載されている(この追悼文はまた追って訳出してお伝えしたい)。 私にとって、映画とは映画館で見るものに他ならず、「なぜ」と考えるのは難しいことです。それはなぜ映画が映画であるのか、と問われているようなものです。勿論、配信やソフトで映画を見ることはあります。ただ、一度でも同じ作品を映画館と家のモニター(+スピーカー)で見比べた体験さえあれば、それらがどれだけ本質的に異なるものであるかについては語るまでもないことと思います。よく、映画には人生を変える力があると言われます。それは間違いではありませんが、実は人生を変える力をより強く持っているのは「映画館」という場の方です。私にとって、自分の人生の方向を根底から変えてしまったと思えるような映画体験はすべて、映画館で起きたものでした。映画館という、集団で映画を見る場のほうが、驚くほど個人の身体に深く決定的に働きかけます。映画館の暗闇が私達の輪郭を溶かしてしまうからでしょうか。繭の中のサナギのように溶かされて、まったく異なる自分に作り変えられてしまいます。映画館に入る前と後では、まったく違う人間であり得ます。映画は身体に入り込んで、自分の人生を支える芯棒のような役割を果たすようになります。そんなにも強烈な変化をもたらす2時間は「劇場」という場以外では生まれ得ないでしょう。
私にとって、映画とは映画館で見るものに他ならず、「なぜ」と考えるのは難しいことです。それはなぜ映画が映画であるのか、と問われているようなものです。勿論、配信やソフトで映画を見ることはあります。ただ、一度でも同じ作品を映画館と家のモニター(+スピーカー)で見比べた体験さえあれば、それらがどれだけ本質的に異なるものであるかについては語るまでもないことと思います。よく、映画には人生を変える力があると言われます。それは間違いではありませんが、実は人生を変える力をより強く持っているのは「映画館」という場の方です。私にとって、自分の人生の方向を根底から変えてしまったと思えるような映画体験はすべて、映画館で起きたものでした。映画館という、集団で映画を見る場のほうが、驚くほど個人の身体に深く決定的に働きかけます。映画館の暗闇が私達の輪郭を溶かしてしまうからでしょうか。繭の中のサナギのように溶かされて、まったく異なる自分に作り変えられてしまいます。映画館に入る前と後では、まったく違う人間であり得ます。映画は身体に入り込んで、自分の人生を支える芯棒のような役割を果たすようになります。そんなにも強烈な変化をもたらす2時間は「劇場」という場以外では生まれ得ないでしょう。



 ジャン=フランソワ・ステヴナンの監督した3本の作品がデジタル修復され、リバイバルされるという知らせは今年最も嬉しいニュースである。俳優としてのステヴナンは誰もが知っており、その出演作のリストは、ジャック・リヴェット、ピエール・ズッカなど妥協することのない映画作家の作品から、『ムーラン署長』などお茶の間で大人気の連続テレビシリーズまでと幅広いが、彼が偉大な映画監督でもあることはあまり知られていない。しかし『防寒帽』(1978年)と『男子ダブルス』(1986年)は過去40年間でもっとも美しいフランス映画の2本であり、実際に観た者だけがそれを知っている。しかしこれほどまでに特異な魅力を持つステヴナンの映画は何と並べることができるだろうか?フランスでは彼がアシスタントについていたジャック・ロジエ、アメリカでは彼が師匠とみなすジョン・カサヴェテスだろう。この二人の師匠にならい、ステヴナンの映画作りはこの上なく冒険的である。社会や映画の規則を放棄し、一見カオス的に見えながら、所作、編集は非常に的確なのだ。生まれ故郷のジョラで山やアルコールを愛し、犬と一緒に歌う人々たちの驚くべき集まり、ステヴナンしか見せることができないフランス、世界が広がっていく。まさにアルコールと空手がステヴナン映画の原動力といえるだろう。
ジャン=フランソワ・ステヴナンの監督した3本の作品がデジタル修復され、リバイバルされるという知らせは今年最も嬉しいニュースである。俳優としてのステヴナンは誰もが知っており、その出演作のリストは、ジャック・リヴェット、ピエール・ズッカなど妥協することのない映画作家の作品から、『ムーラン署長』などお茶の間で大人気の連続テレビシリーズまでと幅広いが、彼が偉大な映画監督でもあることはあまり知られていない。しかし『防寒帽』(1978年)と『男子ダブルス』(1986年)は過去40年間でもっとも美しいフランス映画の2本であり、実際に観た者だけがそれを知っている。しかしこれほどまでに特異な魅力を持つステヴナンの映画は何と並べることができるだろうか?フランスでは彼がアシスタントについていたジャック・ロジエ、アメリカでは彼が師匠とみなすジョン・カサヴェテスだろう。この二人の師匠にならい、ステヴナンの映画作りはこの上なく冒険的である。社会や映画の規則を放棄し、一見カオス的に見えながら、所作、編集は非常に的確なのだ。生まれ故郷のジョラで山やアルコールを愛し、犬と一緒に歌う人々たちの驚くべき集まり、ステヴナンしか見せることができないフランス、世界が広がっていく。まさにアルコールと空手がステヴナン映画の原動力といえるだろう。
 いまだにジャン=フランソワの死が信じられずにいる。2019年に亡くなった映画監督のパトリック・グランペレとも大の仲良しで、今でも毎日のようにふたりの偉大なバイク乗りは私の人生を駆け抜けている。『防寒帽』のことをいつも考えている。この映画では光が決して消えることがなく、戦後のフランス映画史において前例のない作品であり続けている。出会いと横断の映画であり、ストーリーテラーの映画でもあり、ステヴナンは話上手で彼の話は何時間でも聞いていられる。ジャン=フランソワとはジャック・リヴェットのアシスタント時代に知り合いになり、1979年にロッテルダム国際映画祭で本作が上映されるので彼に同行した。ゴダールが講演をしに来ていて、『防寒帽』について、国、地方、ジュラの風景が描かれた映画として、心を打たれたことを長い間語り続け、ジャン=フランソワは感動して涙を流していた。ヴェンダースの『さすらい』(1976年)との親和性、完璧なドイツ語を話すステヴナンがライン川の向こう側で映画を作ることを夢見ていたことも重要だが、アメリカン・ニューシネマの非常に特殊な存在であるモンテ・ヘルマンとの親和性もあるだろう。ふたりはカンヌで出会い、意気投合していた。ステヴナンにはオーソドックスなものは何もない。例えば、私が『リヴェット、夜警』を撮影したとき、出演依頼すると彼はバイクで現れ、リヴェットのことを(通常言われるような)インテリのアーティストとしてではなく、美食家であり、ダンサーのような身体を持つセクシーな男として語ってくれた。1984年にナタリー・バイに依頼されて、(彼女の当時の夫で、フランスのスーパースターの)ジョニー・アリディのコンサートのステージ・マネージャーを務めた時、ジャン=フランソワはほとんど毎晩のように来ていて、夢中になっていた。彼は本物のジョニーのグルーピーだった。彼はフランス映画界では非常に異端な俳優であり、そのころを自覚していた。彼は、マーロン・ブランドやロバート・デュヴァルを思い出させる、つまり、揺るぎない独立性を醸し出しながら、同時に抗い難い魅惑を放つ、完全なる男だった。
いまだにジャン=フランソワの死が信じられずにいる。2019年に亡くなった映画監督のパトリック・グランペレとも大の仲良しで、今でも毎日のようにふたりの偉大なバイク乗りは私の人生を駆け抜けている。『防寒帽』のことをいつも考えている。この映画では光が決して消えることがなく、戦後のフランス映画史において前例のない作品であり続けている。出会いと横断の映画であり、ストーリーテラーの映画でもあり、ステヴナンは話上手で彼の話は何時間でも聞いていられる。ジャン=フランソワとはジャック・リヴェットのアシスタント時代に知り合いになり、1979年にロッテルダム国際映画祭で本作が上映されるので彼に同行した。ゴダールが講演をしに来ていて、『防寒帽』について、国、地方、ジュラの風景が描かれた映画として、心を打たれたことを長い間語り続け、ジャン=フランソワは感動して涙を流していた。ヴェンダースの『さすらい』(1976年)との親和性、完璧なドイツ語を話すステヴナンがライン川の向こう側で映画を作ることを夢見ていたことも重要だが、アメリカン・ニューシネマの非常に特殊な存在であるモンテ・ヘルマンとの親和性もあるだろう。ふたりはカンヌで出会い、意気投合していた。ステヴナンにはオーソドックスなものは何もない。例えば、私が『リヴェット、夜警』を撮影したとき、出演依頼すると彼はバイクで現れ、リヴェットのことを(通常言われるような)インテリのアーティストとしてではなく、美食家であり、ダンサーのような身体を持つセクシーな男として語ってくれた。1984年にナタリー・バイに依頼されて、(彼女の当時の夫で、フランスのスーパースターの)ジョニー・アリディのコンサートのステージ・マネージャーを務めた時、ジャン=フランソワはほとんど毎晩のように来ていて、夢中になっていた。彼は本物のジョニーのグルーピーだった。彼はフランス映画界では非常に異端な俳優であり、そのころを自覚していた。彼は、マーロン・ブランドやロバート・デュヴァルを思い出させる、つまり、揺るぎない独立性を醸し出しながら、同時に抗い難い魅惑を放つ、完全なる男だった。 ジャン=フランソワ・ステヴナンという人物に対して、僕は愛情と、多大なる尊敬を抱いています。彼の監督作品を25歳の時に発見し、大きな影響を受けました。たとえば彼の映画の持つ驚くほどの自由、寛容さ、場所、空間の中に映画を刻み込む様に。幸運にもムードンにある彼の家を訪れ、会う機会を二度ほど持つことができました。彼に演じてほしいと思って書いた役があったのですが、残念ながらその映画は資金が集まらず撮ることができませんでした。ジャン=フランソワは驚くべき人で、みんなでテーブルを囲んでいる時、自分の妻にある話を語り始めたかと思ったら、僕たちの前で次々にその話の登場人物たちを演じ始め、カメラの動きも身体で示し、ひとりの俳優を超えて、彼一人で映画そのものとなってしまう、つまり大道具係、助監督、俳優、脚本家、演出家、現場にいるすべての人になってしまうのです。彼の家、彼の宇宙、彼の大家族の中に迎えられて過ごしたその数時間を僕は生涯忘れることがないでしょう。ジャン=フランソワ・ステヴナンは、目の前にいる人々にとてつもないエネルギーと、希望を与えてくれる人で、彼にとって人生と映画は分かち難く混ざり合っています。ジャン=フランソワは僕の映画、『女っ気なし』と『やさしい人』をとても気に入ってくれていて、そのことをとても誇らしく思っています。
ジャン=フランソワ・ステヴナンという人物に対して、僕は愛情と、多大なる尊敬を抱いています。彼の監督作品を25歳の時に発見し、大きな影響を受けました。たとえば彼の映画の持つ驚くほどの自由、寛容さ、場所、空間の中に映画を刻み込む様に。幸運にもムードンにある彼の家を訪れ、会う機会を二度ほど持つことができました。彼に演じてほしいと思って書いた役があったのですが、残念ながらその映画は資金が集まらず撮ることができませんでした。ジャン=フランソワは驚くべき人で、みんなでテーブルを囲んでいる時、自分の妻にある話を語り始めたかと思ったら、僕たちの前で次々にその話の登場人物たちを演じ始め、カメラの動きも身体で示し、ひとりの俳優を超えて、彼一人で映画そのものとなってしまう、つまり大道具係、助監督、俳優、脚本家、演出家、現場にいるすべての人になってしまうのです。彼の家、彼の宇宙、彼の大家族の中に迎えられて過ごしたその数時間を僕は生涯忘れることがないでしょう。ジャン=フランソワ・ステヴナンは、目の前にいる人々にとてつもないエネルギーと、希望を与えてくれる人で、彼にとって人生と映画は分かち難く混ざり合っています。ジャン=フランソワは僕の映画、『女っ気なし』と『やさしい人』をとても気に入ってくれていて、そのことをとても誇らしく思っています。








 「ミシェル・ピコリ追悼特集」を開催するにあたり、上映したいと思いながら、様々な理由で叶わず涙を呑んだ作品が数多くあった。それでも今回、どうしてもこれは上映すべきと、困難を乗り越えて準備したのがクロード・ソーテ監督、ミシェル・ピコリ主演作品『マックスとリリー』である(本作は日本未公開作品であり、『はめる 狙われた獲物』というタイトルでビデオ発売のみされている)。
「ミシェル・ピコリ追悼特集」を開催するにあたり、上映したいと思いながら、様々な理由で叶わず涙を呑んだ作品が数多くあった。それでも今回、どうしてもこれは上映すべきと、困難を乗り越えて準備したのがクロード・ソーテ監督、ミシェル・ピコリ主演作品『マックスとリリー』である(本作は日本未公開作品であり、『はめる 狙われた獲物』というタイトルでビデオ発売のみされている)。 『マックスとリリー』、底知れぬ人生の深淵へ
『マックスとリリー』、底知れぬ人生の深淵へ
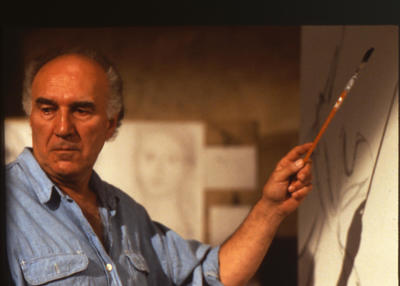 5月12日、フランスの友人からミシェル・ピコリの訃報のメールを受け取った時、とっさに、自分でもすぐに理由が分からずも、涙がこみ上げ、とてつもない喪失感に包まれた。ピコリが、他界、信じられない......。それほどまでにピコリという存在が大切だったこと、その存在をごく当たり前のように感じていたことを、彼がこの世にもういないと知ったその日からひしひしと感じ始めた。ミシェル・ピコリという存在がいかに現代映画にとって重要であり、彼がいたからこそ映画作家たちが作れた映画、生まれた作品があることを確認、再確認するために、追悼特集を組まなければならないとすぐさま企画を提案した。
5月12日、フランスの友人からミシェル・ピコリの訃報のメールを受け取った時、とっさに、自分でもすぐに理由が分からずも、涙がこみ上げ、とてつもない喪失感に包まれた。ピコリが、他界、信じられない......。それほどまでにピコリという存在が大切だったこと、その存在をごく当たり前のように感じていたことを、彼がこの世にもういないと知ったその日からひしひしと感じ始めた。ミシェル・ピコリという存在がいかに現代映画にとって重要であり、彼がいたからこそ映画作家たちが作れた映画、生まれた作品があることを確認、再確認するために、追悼特集を組まなければならないとすぐさま企画を提案した。
 ティップ・トップ ふたりは最高 Tip Top
ティップ・トップ ふたりは最高 Tip Top 赤いトキ L'Ibis rouge
赤いトキ L'Ibis rouge
