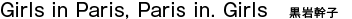パリの街並みを切り取ったファーストカット(たしかY字路だ)からすっと画面に引き込まれた。一度もパリの街に降り立ったことがないのに、その風景にどこか懐かしさを感じる。もしかしたら映画の前に「フィルム・デュ・ロサンジュ」のクレジットを目にしたせいで、その会社をつくったエリック・ロメールの映画をその風景に重ね合わせたのだろうか? 一瞬、そのように自問したのだが、否、ミア・ハンセン=ラブと撮影のパスカル・オフレーによって映し出されるパリの街は、ロメールの映画のそれとは違う色合いを見せている。私が懐かしさを感じたのは、ここで切り取られている街に対してではなく、その画面の色合い、その街並みを映し出す日差しに対してだろうか。この映画には夏の夕方を思い起こさせる、濃いけれどやわらかい光が宿っている。そんな光がどうやってもたらされているのか(自然にそう映っているのか、カメラの露出をいじっているのか)はわからないが、その光にとってもたらされる明暗や色合いはこの映画、この物語にとって欠かせないものとしてある。

この映画は、映画プロデューサーの父親、イタリア人の母親、そして3人の娘たちで構成されるひとつの家族の物語だ。映画の前半、カメラは主に父親に寄り添い、彼が自殺して姿を消してしまう中盤以降は、父親に代わるように長女がその姿をカメラの前に現すようになるのだが、そのふたりが主人公なのではない。強いて言えば、家族全員が主人公ということになるのだろうか。この物語は、誰かひとりの視点ではなく、かといって外側からこの家族を見つめるでもなく、家族を構成する5人の、しかし誰のものとは定まらない視線が混在して語られているかのようだ。
序盤に父親がスピード違反と、無免許運転が見つかって警察に捕まるシーンがある。母親とともに父親を警察署に迎えに行った次女(9歳ぐらいだろうか)が、その帰り道、車の後部座席から、前の助手席に座る父親に、今日あった出来事を喋りかける。暗い車内に響く、要点の定まらない次女のお喋りに、父親が「それはどういうことなんだ?」と、観客である私たちの気持ちをくみ取ったかのようなタイミングで訊ねる。すると次女は彼女なりの言葉で説明を加え、またその先へとお喋りを続けていくのだ。
この何気ない場面で、私は呆然としてしまう。それはふたつのことに気付かされたからだ。ひとつは、私自身もかつてこの少女のように要点の定まらない、終わりがこないような話を両親に向かって喋りまくっていたのだということ、そして、いつの間にか自分が、父親と同じように「それはどういうことなんだ?」と訊ねなければその話の内容を理解できなくなっているということに。このシーンは、子供の話を辛抱強く聞く優しい父親像であるとか、その父親を慕う少女のあどけなさであるとかを伝える以上に、大人と子供の間に横たわる圧倒的な距離を表している。かつて子供だった父親は、すでに自分が子供だったころ何を考えていたかを覚えていないし、我が子が何を喋っているかも100%理解することはできない。そして、次女もまた何故父親が自分の話を理解できないのかわからないし、彼女がこの先大人になった時、自分が父親に向かって喋った話を覚えていないのだ。
彼女がそのこと――父親とかわした何気ない会話も、その時の自分の気持ちもいつか忘れてしまうこと――をまだ知らないということ、そして、そんな彼女に子供のころのことを忘れている自分に気付かされ、私は呆然としたのだ。

父親が自殺をした後、ハイティーンの長女は妹たちを伴って父親の製作した映画を観に行ったり、父親の残した手紙を読み、そこから知った異母兄弟に会いに行ったりする。また、母親は、父親が残した仕事を引き継ぎ、スウェーデンで撮影中の映画監督や、負債を負っている現像所の所長に会いに行く。私たち観客もまた、彼女たちを通して、父親の生前に知ることがなかった彼の映画や秘密、彼の仕事相手に出会っていくことになるのだが、そこから自殺の理由や彼の新たな人柄を推し量ることはできない。そして、彼女たちにとってもそれは同じなのだと思う。彼女たちは、自分が父親(あるいは夫)のすべてを知らなかったこと、すべてを知ることなんてできないことを受け入れることで、彼をその不在とともにもう一度愛することができるようになっていくように見える。
スウェーデンの田舎道を走る車の中で静かに涙を流す母親、朝帰りの帰り道にカフェでひとり静かに物思いにふける長女。そこには父親が生きていた前半ではほとんどかからなかった音楽が大きな音で流れているのだが、彼女たちがひとりで佇むその姿を通して、私たちは彼女(たち)の夫(父親)の存在をこれまで以上に強く感じることになるだろう。それはきっと彼女たちが彼がいないことを受け入れたことによって、彼が(彼女たちの人生の中で)再び生き始めたからだ(これらのシーンは『そして僕は恋をする』で、アルノー・デプレシャンが主人公と別れたエマニュエル・ドゥヴォスの生活を淡々と切り取っていったシーンに匹敵する美しさだ!)。

この映画が秀逸なのは、この長女と母親がひとりで佇むシーンから、幼い次女や三女にもいつかこのような瞬間が訪れることが予感される点にある。あるいは父親が次女と三女に聖堂の絵画について説明をするシーンを観ると、彼がその場にはいない長女にもかつてこのように絵画について話して聞かせた時があったのだと感じられる。父親がその死後も家族の存在によって映画を生き続けているように、母親と娘たちも画面に現れなくても、他の家族の姿によって常にその存在を私たちに感じさせるような、そんな映画なのだ。
もっと言えば、この映画は娘たちの現在の眼差しと、自分が子供だったころを忘れてしまった、大人になってからの未来の彼女たちの眼差しの両方でできているように思う。やわらなか光でつつまれたパリの街並みや、郊外の川沿いの道、イタリアの森、逆に深い暗闇が覆った、別荘の庭の木々、映画館の客席、停電の夜。光と闇によって映し出される数々のシーンは、私たちに子供のころを思い出させ、また、その思い出が光と闇によって記憶されていることに気づかせてくれる。この映画に出てくる娘たちは、そこに流れている今の時間を少しずつ忘れていくだろう。それでも、川沿いの道を散歩する時、停電になって蝋燭に火をともす時、自分の子供と聖堂の絵画を見る時、目の前に広がる風景の光や影、その色合いによって、自分が子供のころのことを思い出すのだ。そして、その思い出のなかには父親の姿がある。だから、父親は彼女たちの中に生き続ける。そう、「特に私たちの中に!」。
映画の最後、母親と娘たちを乗せた車がパリの街を走り去っていく。冒頭のパリを照らしていたやわらかな光が闇の訪れとともに次第に弱まり、車のヘッドライトや街灯が色づき始めている。彼女たちはこの街の景色を忘れる。でも、いつか同じ場所に降り立ったときに、この時の景色をかすかに思い出す。自分がこの景色を忘れていたことを思い出す。この景色もそうやって彼女たちの中に生き続ける。だからこの映画に映るパリの街は懐かしく、そして新しいのだ。